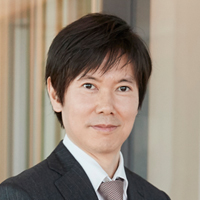CONTENTS
- 2017年はRPA認知が急拡大
- RPAをどう理解するか
- RPAの導入実態は
- RPAによって今後何が変わるのか
- RPA導入の推進主体はユーザー部門かIT部門か
- テクノロジーは仕事を奪う悪魔か
要約
- 2017年は日本でRPAの認知と導入が急速に広がり、今後のさらなる拡大を予感させる年となった。RPAは、物理的な実体のないソフトウエアであり、人間がPCを介して行っている作業を代行する存在である。産業用ロボットやITシステム、AIとは異なる機能・役割を持つが、相互に連携し合いながら発展していく可能性が高い。
- RPAは導入ハードルが低く、部分的な効果はすぐに得られるが、それを「業務コスト削減」「顧客対応力強化」「働き方改革」などの経営課題に対する解決策にまで昇華させるためには、個々には小さな導入効果の収集とターゲット領域への再投下のための段取り整理が不可欠である。
- 今後のRPA活用を前提とすると、人間とロボットの役割分担や作業順序変更が生じ、事務オペレーション設計の考え方を変える必要が出てくる。また、それによって企業経営の基盤である人材やITシステムのあり方も見つめ直す必要が出てくる。
- RPAの適用対象業務は小粒で個別性が強いことが多い。そのため、必要なロボットの数や導入スピード、ロボット停止時の業務復旧スピードなどを考えると、導入においてはIT部門だけに頼るのではなくユーザー部門が主導すべきである。しかしながら、かつてのEUCと同様、RPAの展開時には業務統制面でのリスクを抑えるための役割・責任の分担や、ルール・標準類の整備などが不可欠である。
- AIやRPAのような先端テクノロジーが人間の仕事を奪うという予測・研究もあるが、歴史的に見てもテクノロジーは仕事の新陳代謝を促進する存在のはずであり、それを実現させる経営のビジョンと実行計画こそが重要なのである。
PDFファイルでは全文お読みいただけます。
執筆者情報
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。
購読に関するお問い合わせ先
年間購読をご希望される方は、下記問い合わせ先へお願いします。
-
NRIフィナンシャル・グラフィックス
戦略マーケティング部
Tel:03-5789-8251(平日9:30~17:00) Fax:03-5789-8254※FAXでのお問い合わせは下記お申し込み用紙をご使用ください。
お申し込み用紙ダウンロード(236KB)