日本企業のROEはグローバルに見て低い水準のまま。昨年制定された「日本版スチュワードシップ・コード」は、企業価値向上の責務は投資家にもあるという考えに基づくものだ。投資家は企業を変革させることができるのか、それにはどのようなスキルセットが必要なのか、「働く株主」を社是とするみさき投資の代表取締役社長 中神氏に語っていただいた。

語り手
みさき投資株式会社
代表取締役社長
中神 康議氏
1986年 アンダーセンコンサルティング(現、アクセンチュア)入社。その後、コーポレイトディレクションのパートナーとして、約20年弱にわたり幅広い業種で経営コンサルティングに取り組む。2005年に投資助言会社を設立し社長就任後、約8年半、本格的なエンゲージメントファンドを運用してきた。2013年10月 みさき投資株式会社を設立。「みさきエンゲージメントファンド」の運用を開始。

聞き手
株式会社野村総合研究所
金融ITイノベーション研究部 上席研究員
堀江 貞之
1981年 野村総合研究所入社。96年~2001年野村アセットマネジメントに出向。現在、大阪経済大学経営情報研究科大学院客員教授。2013年8月から金融庁「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」メンバー。2014年4月からGPIFの運用委員会・運用委員長代理。8月より「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」メンバー。
経営コンサルタントから投資家へ
堀江:
みさき投資は、「働く株主」を標榜した非常にユニークな運用会社です。中神さんのバックグラウンドも含めて、みさき投資のコンセプトを教えていただけますか。
中神:
私は、大学を卒業してすぐ経営コンサルティング業界に入り、20年間にわたって会社の経営を少しでも良くする、ということを仕事としてきました。実際、20年もやっていると、コンサルタントと経営者の間ですごくいい仕事ができると、劇的に会社が変わる、会社が変わると価値が上がる、その価値が株価に反映する、という経験が何回もありました。
そこでこれからは、投資家として汗をかいて会社を良くする、それによってリターンを提供する、ということをやってみたいと思ったんです。それが「働く株主」というコンセプトです。
堀江:
コンサルタントと投資家としての仕事は、専門性や経営者との関わり方でどういう違いがあるんですか。
中神:
経営コンサルティングは受注産業という側面があるんです。クライアントサイドに何か問題意識があって、「社内では解き切れない」あるいは「第三者の視点が欲しい」ときに、経営コンサルタントに話が来るわけです。
投資家の場合は逆で、「ここが問題ではないですか?ここは、もうちょっと改善できるのではないですか」というようにこちらから能動的に提案をしていくことになります。
ただ、基本的なスキルセット、例えば経営者を説得するロジックの立て方、等は変わりません。
堀江:
会社側が問題意識を持って、自らお金を払って頼んでいるケースとは違い、「投資家になりました。おたくはこうしたらどうですか」と言われると、経営者はどのような反応になるのですか。
中神:
「そんな提案は要らない」と言われる経営者も、中にはいらっしゃいます。逆に、「株主は結果責任という意味で「同じ船」に乗っているので大歓迎」と言ってくれる経営者も数多くいらっしゃいます。
堀江:
それは、業種によって差が出るものですか。
中神:
業種や企業サイズではなく、経営者のマインドセットが大きいと思います。これは我々が考えた言葉なのですが、経営者として“HOP”の資質を備えた方、すなわち、会社を改革し成長させることに貪欲(Hungry)であること、そのためには外部の意見もどんどん取り込んでいこうという開かれた姿勢(Open mind)があること、そして、上場公開企業(Public company)として意識がある人は、どんどん話を聞かせてくれという方が多いです。
投資先企業に欠かせない経営者の“HOP”
堀江:
伝統的な運用会社と中神さんの会社では、投資に至るまでのプロセス、その後の向き合い方にどのような違いがあるのでしょうか。
中神:
会社に「価値」と「価格」があるとしたら、私たちは「価格」のほう、少なくとも短期の株価を当てることが得意だとは思っていません。
しかし、企業の「価値」のほうは、当たらずとも遠からずのレベルで理解できると考えています。会社の価値は、会社が生むキャッシュフローの頑健性からくるものです。それは、徹底的に企業や業界について調査、分析を行い、競争力を洞察することでおおよそ推定できると考えています。
堀江:
そうやって選定された会社に投資をしていくんですか。
中神:
今申し上げた競争力、キャッシュフローのほかに、経営者が“HOP”かどうかを見ます。ですから、経営者の方にも必ずお会いします。この事前調査フェーズに1、2ヶ月費やします。
そのあと、2段階に分けて投資を行っていきます。まずはドアオープン投資という段階です。ここで投資をスタートしながら、大体6カ月から10カ月ぐらい調査を行います。この間に経営者とも議論を重ねます。
ドアオープン投資をする中で、競争力・経営者、さらに、私たちが経営に貢献できるかをよく見て、そこに確信が持てたら、コア投資に移ります。コア投資になれば、長期投資、エンゲージメント投資になっていきます。
堀江:
長期投資でよくあるのは、経営者との対話はやらずに、長期にキャッシュフローを生み出す能力が高いことを見極めて、長期のバイ・アンド・ホールドで集中投資をするタイプです。
中神:
誰が経営しても価値を生み出す会社に投資する、というバフェット的な考え方ですよね。
堀江:
経営者との対話が加わることで、キャッシュフロージェネレーションの能力を高めていくことが本当にできるものなんでしょうか。
中神:
経営コンサルティングを長年行ってきた実体験からすると、十分可能だと思っています。
堀江:
自分達の意見を経営に反映してもらうには、ある程度ポジションを大きく持たなければいけないといった条件があるのではないかと思いますが。
中神:
規模とか持ち株比率は、大きな条件だとは思っていません。一方で、経営者とよい関係を築き価値を一緒にあげていくには3つぐらいの要素があります。
一つは相手の選び方で、やっぱり経営者のHOP。これはもう大前提です。HOPでないと、一緒になって価値を上げる、会社を変えることはできません。
二番目は、投資家サイドの問題で、重要性の高い経営課題に対してクオリティの高い提案を持っていくこと。経営者には、いろんな提案が持ち込まれるわけですから、「聞くに値する話」を持っていかなければ、相手には刺さりません。
三番目も投資家サイドの問題で、経営者に自分のアイデアを「売る」、すなわち、それは確かにやってみると面白いかも、と思わせるためのノウハウやスキルセットです。
堀江:
日本の経営者でも、ちゃんと聞いてくれる素地はありますか。
ひところ、日本企業に対する海外のいわゆるアクティビストの活動が話題になりました。私自身は、まともな提案だと思うものも結構あったと認識しています。しかし、うまくいかなかった。その理由はどういうところにあるんでしょうか。
中神:
まず相手を間違えているのではないかと思います。HOPではない人に言っても無駄です。また、提案自体も、例えば単に資本政策だけに限定した話であれば、経営からしてみれば重要度は必ずしも高くなかったり、どの投資家がしてもそんなに変わらず、「ああ、いつもの話ね」ということで片付けられてしまうかもしれません。
要は、三番目のところだと思うんです。なぜそういう提案に至ったかを、経営者の立場に立ち、事実を徹底的に集め、説得力を持って語ったかです。人間を動かしたいのなら、相手の立場に立って話す必要があります。過去のアクティビストの失敗は、一番目の選定要素と三番目の説得力がまずかったのかなと思っています。
堀江:
やっぱり人対人のリレーションシップが非常に重要だということですね。
中神:
そう思います。経営にとって、人のバリューの影響は大きいです。会社は経営者によって、驚くほど変わります。
私達は、経営者を見て投資していますし、経営者と投資家の関係をものすごく大事にしています。
堀江:
HOPの経営者であれば、投資家側が、クオリティの高い提案を、説得力を持って話すことができれば、ビジネスの価値を上げられる企業は、結構あるということですか。
中神:
その通りです。
日本企業の低マージン性
堀江:
バランスシートの右側は、財務戦略も含めて、日本の企業は未熟な部分が多くて、改善の余地が大きいと見られています。また、短期的にも即効性のあるソリューションが右側のほうにはあると思います。
けれども、中神さんは、そこも当然やるけれども、バランスシートの左側の、ビジネスそのもののストラクチャリングの改善を図っていきたい、ということですよね。
海外の方の意見を聞くと、「日本企業は、左側は結構ちゃんとやっているので改善余地が少ない。それに対して、財務戦略を含めた右側は、欧米の会社に比べて拙い部分が多いので、時間軸で考えると、そちらをやったほうが効果的」という意見が多いです。
中神:
それはよく言われる話ですが、本当にそうなのでしょうか?例えば資本の生産性をデュポン分解したときに、財務レバレッジとか資産の回転率は、欧米各国とあまり変わりません。逆に、圧倒的に低いのが事業のマージンです。ですから、本当にいいエンゲージメントをしようとしたら、どうしても核心はここに置くべきだと思うんです。
資本政策だけ、バランスシートの右側だけで価値と価格のギャップを埋めるというのは手っ取り早いし、確かに一定の効果もありますが、そのインパクトは実はせいぜい2~3割です。しかも、それはワンショットの一時的効果で終わります。一方、例えば、我々の成功事例のひとつであるピジョンさんでは、海外成長によって事業価値そのものが大きくなっているので、時価総額で見ても7~8倍になっています。単なる資本政策の改善とはインパクトの大きさが全く違うんです。
堀江:
日本企業の問題はマージンの低さであり、そこに手をつけるような改革をしないと大きくは変えられない、ということですね。
中神:
英語で“lowhanging fruits”という言い方がありますよね。手の届く場所に成っている実を食べていれば、確かに当面は暮らせるけれども、木そのものを大きく成長させなければ採れる実はすぐになくなってしまう、ということです。それと同じだと思うんです。
堀江:
日本企業の低マージン性の理由はどこにあるんでしょう。
中神:
これも諸説紛々ですが、私は、レイヤーが4つぐらいあると思っています。
まずは、制度上の問題。のれん償却や法人税等、日本の会計や税制の特殊性に起因する部分です。二番目は、業界レベルの話で、特定産業でプレーヤーが多過ぎて、過当競争になっていて疲弊してしまうという問題です。この2点は確かに問題として存在しますが、低マージン問題の本質的なポイントではないと思います。
やっぱり本質的な問題は企業経営そのものであり、そこは2つに分けています。まずは、全社レベルの問題として、事業・製品のポートフォリオ管理が緩いという点です。
堀江:
それはマージンが低いものでも持ち続けているという問題ですね。
中神:
そうです。弊社の経営諮問委員でもある楠木教授的に言えば、Q(クオリティ)企業、O(オポチュニティ)企業という話です。クオリティ企業は、一つの事業・強い製品を徹底的に磨き上げ、グローバルで戦って利益率を高く保つ。一方、オポチュニティ企業は、市場のあちこちで生まれる市場機会を、それが限界的なものであってもとにかく全部取りにいく。結果として事業が分散してしまう、あるいは製品数が多くなってしまう。
例えば、自動車メーカーを見ても、日本の会社は、モデル数が多く、モデルチェンジも頻繁です。これは、自動車だけではなくて、食品・飲料、あるいは携帯電話端末、家電、等々数多くの産業で見られる現象です。
堀江:
小さいオポチュニティでも全部、自分たちでやりたい・取り込みたい、という企業が日本には多い。
中神:
でも、そうすると何が起きるでしょうか。製品や事業の数が多いと経営資源が分散しますよね。製品ごとに営業効率が分散する、新製品を出すためには新たに研究開発費もかかる、新しくラインを作ると減価償却も乗ってくる、製品ごとの広告宣伝費は限られる。一方で一品ごとの製造規模が取れないので、原価も高いんです。
コカ・コーラやケロッグ、アップルなどを見ると、無闇にマージナルなニーズを取りにいっていません。少数の「これで勝負する」というものを決めているんです。自分の強みが生きる限られた事業・限られた製品にだけ集中し、しっかり広告宣伝費や営業コストをかける。それが売れれば、製造規模が働くので、原価が低く抑えられ、十分な利益が生まれる。経営の根本思想が違うんです。
企業経営の問題の2点目は、ぜんぜん違う切り口なのですが、「経営者≒投資家」という理解が不十分という問題です。経営者は、もちろん事業経営や組織運営を行っているわけですが、裏面では投資家そのものだと思うんです。高度な経営判断とは、要は「どういう資金調達が今、最も安価で、その最も安価なお金を使って何に投資をするのか」ということですよね。極めて投資家的ではないですか。設備投資をするのも投資だし、M&Aをするのも投資ですが、一方で自社株買いも投資です。安易な成長シナリオが描きづらい時代観の中で、経営者に「何で調達して、何に使うべきか」という投資家マインドが弱い気がします。
今、本当に新しい製品を出すのがいいのか、そのために減価償却が増えるけれどもまた工場を建てるのがいいのか、株価があまりにも安いのであればむしろ自社株買いしたほうが投資対効果は高いのではないか、といった投資テーマがいろいろあるわけです。
日本には、これだけいい製品・サービスがあるのに、なんでこんなに利益率が低いの?と。そこには「経営」というクッションがあって、そこがもっとよくなれば、もっともっと利益率は高まると思うんです。
ですから、元コンサルタントの我々としては、事業そのものに踏み込んで提案することで、企業価値があがる余地はまだまだ大きいと思っています。
有価証券報告書からガバナンスを読み解く
堀江:
私も委員で入っていましたけれどもコーポレートガバナンス・コードというのがありますね。
私は、外形的な基準が企業価値に利くとは思っていないんですが、しかしながら、「最低限の条件」はあると思うんです。コードには、その最低限のものを入れたつもりです。
中神さんが投資されている企業は、既にあのレベルの話は終わっているのでしょうか。企業価値を上げる上での活動にはあまりインパクトはないのでしょうか。
中神:
ガバナンスの改善は「やったほうがよい」テーマだとは思いますが、企業価値を上げるという点で主従関係の「主」ではないと思います。
私たちは、「ガバナンスがいい会社だったら投資するのか」というと「ノー」です。逆に、「ガバナンスが悪い会社だと投資しないのか」というと、それも「ノー」なんです。
一方で、ガバナンスのことは実はよく見ています。では何を見ているかというと、経営に対する真摯な姿勢、つまり、この会社は経営のすみずみ・端々まで手を抜かずによく考えている会社かどうか、というシグナルを見ているといったほうがいいかもしれません。ガバナンスや株主還元といったテーマは、経営にとってはおざなりに済ませることもできなくはないテーマです。そんなテーマでも経営がしっかり考え抜いて、自分たちなりの答えを出しているとするならば、それはとても良いシグナルなんです。
堀江:
シークレットにならない範囲で、例えば、どういうところを見ているのか教えていただけますか。
中神:
全然、シークレットでも何でもありません。有価証券報告書やアニュアルリポートを読み込んで見れば、はっきり分かります。
堀江:
有価証券報告書を読んだだけで、分かりますか?
中神:
もうびしびし伝わってきます。堀江さんだって、運用会社が出しているスチュワードシップ・コードの受け入れ表明を見たら、考え抜いて書いたのかどうか分かるんではないですか。
堀江:
それははっきり分かります。
中神:
それと同じです。ガバナンスのところまで突き詰めて考えていて、自分の言葉で経営している会社かどうか。それはわれわれのような経営の質に投資する投資家にとっては、ものすごいグッドサインです。
堀江:
そうすると委員会等設置会社であろうが監査役設置会社であろうが、外形的な基準は全く関係ないですね。
中神:
関係ないです。
堀江:
そうすると、企業に対するメッセージは「あまり外形基準にとらわれずに、自分の言葉で書くべきだ」ということになりますか。
中神:
そうだと思います。
突き詰めて言うと、経営の大敵は「思考停止」だと思います。「なぜあの会社はROEがこんなに高いんだっけ」「なぜ今、ガバナンスが問われるのか?」「なぜ海外の競合はここまでレバレッジを効かせているのか?それは本当に正しいのか?」といった疑問には、学びのチャンスがものすごくあるではないですか。だから、今のやり方が一番いいんだと思わずに、虚心坦懐に他社や他国から学び、自分なりに経営を工夫するというのは、経営にとって一番大事なことだと思います。他社がやっているからという横並び・Me-Too的な思考、過去そうしてきたからという前例主義が大敵なんでしょうね。
堀江:
企業経営者はどのようにメッセージを伝えればいいんでしょうか。私自身は、Berkshire Hathawayのウォーレン・バフェットのshareholder’ lettersとか、J.P.モルガンのジェイミー・ダイモンのshareholders’ letterといったCEOが株主に宛てたレターから学ぶことが多いです。
中神:
書き物だけで表現できるかというと、そうではないと思います。中には書くのが苦手な人もいます。ですから、これも外形にこだわらずに、伝えやすいと考える手段で発信していけばいいと思います。例えば、株主総会の時に語ってもいいですし、新聞記者に話す機会でもいいと思います。
堀江:
日本は、どちらかというと形にこだわる人が多くて、CSR報告書であったり、コーポレートガバナンスの報告書であったり、統合報告であったり。
中神:
それは、受け手側が楽をしたいからではないですか?投資家サイドも、思考停止してしまっていて、「これさえ読めばいいものを作ってくれ」みたいな話になってしまうのは良くないです。本当にいい投資をしたいのだったら、やっぱり、自分達固有の方法で徹底的に調べる必要があると思います。
堀江:
まだまだお聞きしたいことが山ほどあるのですが、時間がきてしまいました。本日は、貴重なお話をありがとうございました。
中神:
こちらこそありがとうございました。
私たちは投資家として、HOPな経営者に、フレッシュな第三者の視点を提供し経営進化に貢献していきたいと思います。
(文中敬称略)
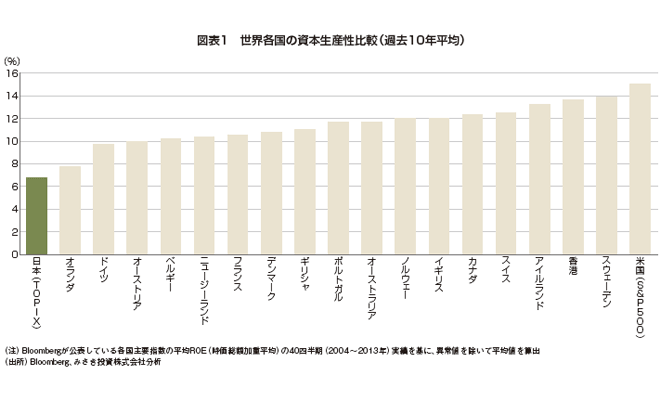
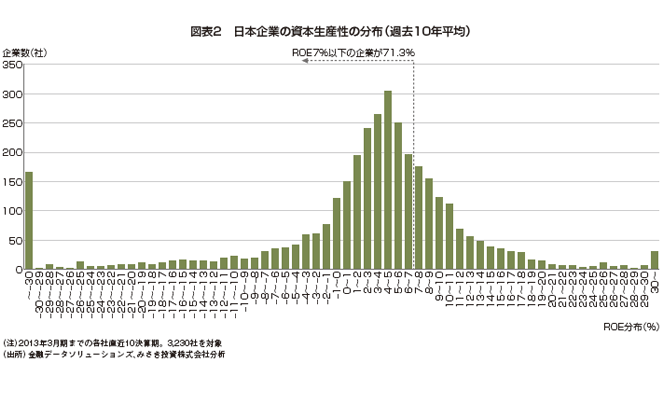
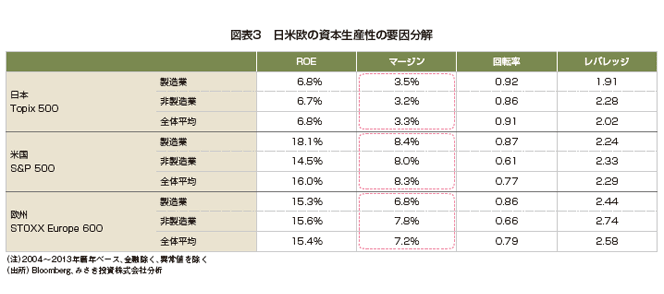
ダウンロード
可能性を秘めた企業の発掘
ファイルサイズ: 1.32 MB