2021年のベースアップ率はほぼ0%に
2021年の春闘(労使交渉)が始まった。コロナショックによる急激な雇用情勢の悪化を受けて、今年の春闘では雇用を守ることに重きが置かれる結果、賃金上昇はかなり抑えられる可能性が高い。
経団連の集計によると、2020年の賃上げ率はちょうど+2.00%だった。このうち定期昇給分の引き上げ率が+1.83%、ベースアップ率が+0.17%という内訳だ。定期昇給分は安定しており、近年は毎年+2%弱の水準である。
春闘で注目が集まりやすいのは、ベースアップ率だ。ベースアップ率は、リーマンショックの影響から2012年まではほぼ0%だった。その後は改善傾向を示したが、2018年の+0.46%をピークに、2019年に+0.37%、2020年には+0.17%まで上昇率を低下させてきた(図)。
2021年の春闘で連合は、昨年までと同様に2%程度のベースアップを要求しているが、実態としては2%程度の定期昇給分の引き上げをなんとか確保することが基本戦略だろう。実際のベースアップ率は、0%に近いわずかなプラスとなると見込まれる。そうなれば、2012年以来9年振りの低水準となる。
図 春闘ベースアップ率の推移
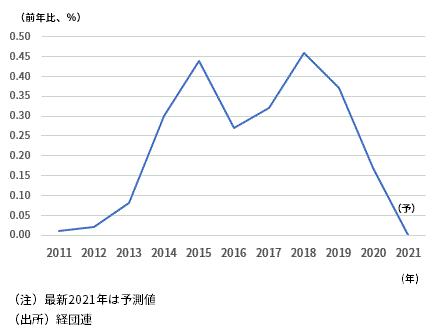
2020年冬のボーナスは前年比-9%
日本では、いくら経済・雇用情勢が悪化しても、ベースアップ率がマイナスになることはまずない。所定内賃金には強い下方硬直性があるのだ。その分、労働時間とボーナスで、人件費の調整が行われる。
2020年の冬のボーナスは、経団連の調査によると前年比-9.02%と8年振りの低水準となった。2019年の冬のボーナスは前年比+1.77%、2020年夏のボーナスは、同-2.17%であった。2019年の実績に基づいて計算すると、ボーナスなど特別給与は、給与全体の18.1%と2割弱を占めている。ボーナス支給の状況は、経済環境に遅れる傾向が強い点を踏まえ、仮に今年2021年の夏と冬のボーナスも、平均すると2020年の冬のボーナスの前年比増加率に一致すると仮定すれば、ボーナスの削減だけで、2021年の一人当たり給与総額は前年比で1.6%減少する計算となる。
定期昇給分を含めた2021年の賃金上昇率は+2%程度となろうが、定期昇給分の賃金上昇は、個々人のベースでは賃金上昇となるものの、労働者全体の平均でみれば賃金上昇につながらない。賃金水準が高い退職者が、賃金水準が低い新規労働者に置き換えられていくためだ。
そこで、定期昇給分を除いたベースアップの上昇率は、所定内給与全体の上昇率と比較的近い水準となる。ベースアップ率が0%に近いもとでは、2021年の所定内賃金上昇率はほぼゼロになるだろう。
2021年給与総額は前年比-1.6%程度が目途か
他方、昨年11月時点では、残業代に相当する所定外給与は、前年同月比-12.8%と大幅減であった。ただし、2021年は経済環境が年後半に改善傾向を辿るなか、年間平均では残業時間は前年比と同水準となり、一人当たり所定外給与も同様になると考えよう。
このように、経済・雇用環境の一定程度の改善を前提に考えても、ベースアップ率がゼロ、経済・雇用環境に遅れるボーナスの上昇率が前年比-9%となる場合、2021年平均の一人当たり給与総額は、前年比-1.6%程度となる計算だ。
ちなみに2019年の一人当たり給与総額の実績は前年比-0.4%、2020年は推定で同-0.6%である。2021年の数字が前年比-1.6%程度となれば、それは、リーマンショック時の2009年の-3.8%以来の低水準となる。また、過去30年間では、2009年、2002年に次いで3番目に低い数字となる。
感染拡大に歯止めがかかるなか、経済情勢は2021年後半から緩やかに持ち直していく姿が現状では展望できるものの、このような厳しい所得環境が、個人消費の回復の足かせとなり、経済の回復力を確実に削ぐことが見込まれる。
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。