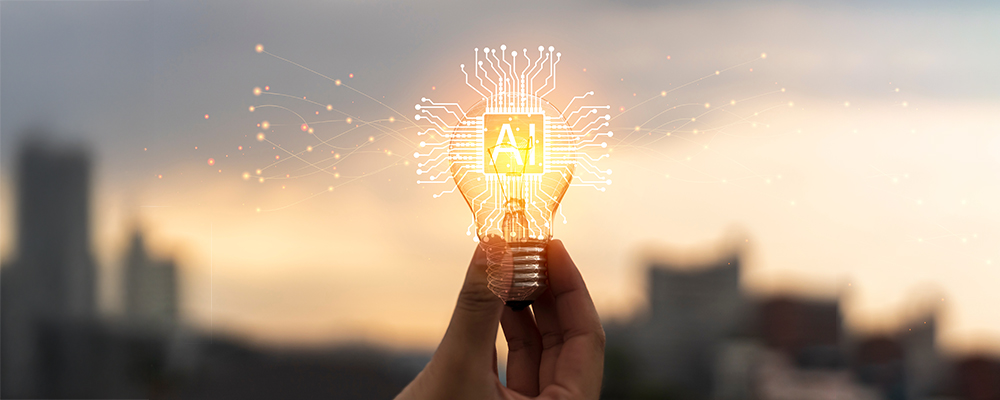
執行役員 産業ITイノベーション事業本部副本部長 生産革新センター副センター長 内海 朋範
春、ゴールデンウィークの頃になると、田舎の実家の庭には無数のモミジの芽が地表から顔を出す。草刈りを終えた庭のあちこちで生えた小さなモミジは、まだ本葉が2枚ほどしかないうちから、すでにその特徴を現している。
モミジは他家受粉(ほかの個体の花粉により受粉)であり、遺伝的な変異が起きやすい。そのため、たとえ美しい葉を持つモミジから生まれたとしても、子が親の特徴をそのまま引き継ぐとは限らない。まだ幼いモミジたちは一見似ているもののそれぞれ個性豊かであり、中には親とは全く異なり、春から葉が深い朱色に染まる個体もある。葉の形についても、丸みを帯びたものから切れ込みの深いものまであり、色と形の組み合わせは多種多様である。
子供の頃、父とともに無数に芽吹いたモミジの新芽の中から、葉の色が濃い赤みを持ち、葉の形が深い切れ込みを持つ個体を探し出し、植え替え育てたものである。地面を見つめながら庭や裏山を歩き回り、数多くの新芽の中からより美しい個体を見つけ出す。それを父から褒められた経験は、この季節になると思い出す子供時代の一種の宝探しのような記憶である。
進化するAI技術、創造性を巡る可能性と脅威
このように、自然界では進化と変化が絶え間なく行われているが、私たちの社会でもAI技術の目覚ましい進化により日々新たな技術やモデルが生まれてきている。その急激な変化に対しては、昨日までできなかったことが明日にはできるかもしれないという思いを多くの人が感じているだろう。「知力」としてのAIの幅は日に日に広がり、それ故、AIに寄せられる期待が高まり、活用事例やそこから生まれる成果物も日々増加している。一方、その急速な進化ゆえに、人間の仕事や役割を奪う脅威として捉えられる面も大きくなっている。
野村総合研究所(NRI)ではAIがもたらす知力を、①予測力、②識別力、③個別化力、④会話力、⑤構造化力、⑥創造力、の6つに分類している。特に⑥の創造力については、人間の知的創造性への脅威として捉えられる場合が多い。たとえば、AIによってつくられた模倣コンテンツの氾濫などは、新たな創造物を生み出すことを阻害するものとして心配する声が出てきている。先日も日本の有名アニメ風画像をAIで生成することが一種の世界的ブームになっているとの記事を読んだ。これに対しては、AIの能力の高さを驚嘆する声とともに、誰もが簡単にある程度のクオリティを持つコンテンツを一瞬でつくり出してしまうことに対し、さまざまな問題提起がなされた。AIが人間と比較して優位な点は、成果物を圧倒的に短い時間でかつ大量に生産できることである。モミジが春、一斉に数多くの異なる芽を地表から生やすかのごとく、AIはさまざまなパターンの成果物を無数につくり出すことができるのである。
野村総合研究所(NRI)ではAIがもたらす知力を、①予測力、②識別力、③個別化力、④会話力、⑤構造化力、⑥創造力、の6つに分類している。特に⑥の創造力については、人間の知的創造性への脅威として捉えられる場合が多い。たとえば、AIによってつくられた模倣コンテンツの氾濫などは、新たな創造物を生み出すことを阻害するものとして心配する声が出てきている。先日も日本の有名アニメ風画像をAIで生成することが一種の世界的ブームになっているとの記事を読んだ。これに対しては、AIの能力の高さを驚嘆する声とともに、誰もが簡単にある程度のクオリティを持つコンテンツを一瞬でつくり出してしまうことに対し、さまざまな問題提起がなされた。AIが人間と比較して優位な点は、成果物を圧倒的に短い時間でかつ大量に生産できることである。モミジが春、一斉に数多くの異なる芽を地表から生やすかのごとく、AIはさまざまなパターンの成果物を無数につくり出すことができるのである。
AIと共に築くクリエイティブな未来と人間らしさ
クリエイティビティが求められる業界の一端を担っている弊社としても、これは他人ごとではない。私たちの業務は、コンサルティングはもちろんのこと、システム開発においても単純な生産活動ではない。お客様の課題から真の課題を見つけ出し、そこから創造力を働かせ、その解決のための方策やシステムを提案・構築することが求められる。その意味では、われわれも「創造力」という知力の分野でAIの影響を受ける当事者の一人といえる。AIの創造力は私たちの業務を支援する大いなる力である一方、私たちの業務をディスラプトする可能性がある脅威でもある。私たちは、そのような創造力という知力を持ったAIとどのように向き合うべきなのだろうか。
考えてみると、これまでの産業の発展はいかに短期間に低コストでアウトプットを生み出すかというものであった。その意味では、生成AIが人間の過去の成果やノウハウを学習し、短期間に低コストで大量創造していくことは避けられないことであろう。私たちはそこから、いかに人間らしく非連続なイノベーションを生み出し獲得していくのか、これまで以上に人間ならではの力が求められていくのではないだろうか。あたかも無数に芽生えたモミジからより美しい個体を選び出し成木に育てていくように、AIによる数多くの試行で芽生えた創造物の中から新たな気づきを得、そこからイノベーションを育てていく、AIの創造力と人間の創造力、それぞれの長所を活かしながら協力していくことが必要となる。その行為は、人間が多くの経験とそこから得た記憶、そしてそこから生まれる価値観によってつくり出されるものであり、創造力を持つようになったAIと協業していくには、これまで以上に論理を越えたアートな感性が問われることになると感じる。
今年のゴールデンウィークも私の実家には無数のモミジが発芽した。父と同じように、今度は私が息子と色と形がよい芽を探しながら、ふと、この経験や記憶、そして論理を越えた親子の共通の価値観がAIに取って代わられるのはまだまだ遠い先であってほしいと感じた。そして何よりも息子がこの経験を子供時代のよき記憶の一つとして頭の片隅に残しておいてほしいと願うのであった。
考えてみると、これまでの産業の発展はいかに短期間に低コストでアウトプットを生み出すかというものであった。その意味では、生成AIが人間の過去の成果やノウハウを学習し、短期間に低コストで大量創造していくことは避けられないことであろう。私たちはそこから、いかに人間らしく非連続なイノベーションを生み出し獲得していくのか、これまで以上に人間ならではの力が求められていくのではないだろうか。あたかも無数に芽生えたモミジからより美しい個体を選び出し成木に育てていくように、AIによる数多くの試行で芽生えた創造物の中から新たな気づきを得、そこからイノベーションを育てていく、AIの創造力と人間の創造力、それぞれの長所を活かしながら協力していくことが必要となる。その行為は、人間が多くの経験とそこから得た記憶、そしてそこから生まれる価値観によってつくり出されるものであり、創造力を持つようになったAIと協業していくには、これまで以上に論理を越えたアートな感性が問われることになると感じる。
今年のゴールデンウィークも私の実家には無数のモミジが発芽した。父と同じように、今度は私が息子と色と形がよい芽を探しながら、ふと、この経験や記憶、そして論理を越えた親子の共通の価値観がAIに取って代わられるのはまだまだ遠い先であってほしいと感じた。そして何よりも息子がこの経験を子供時代のよき記憶の一つとして頭の片隅に残しておいてほしいと願うのであった。
プロフィール
-
内海 朋範のポートレート 内海 朋範
執行役員
産業ITイノベーション事業本部 副本部長
生産革新センター 副センター長
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。