
木内登英の経済の潮流――「景気後退への備えに不安」
来年以降の世界経済に慎重な見方が増えてきました。仮に近い将来、世界経済が悪化する場合でも、金融緩和策で対応できる余地がかなり小さいことが、見通しをさらに厳しくしています。
日欧で追加緩和の余地は小さい
世界経済がこの先悪化し、また後退局面に陥ったとしても、各国ともに金融緩和で対応できる余地は限られています。主要中央銀行の中でECB(欧州中央銀行)と日本銀行は、長らく金利政策の限界とされてきたゼロ金利制約を打ち破り、マイナス金利政策を導入しました。しかし、それによって、中央銀行が限界のない政策手段を手に入れたと考えるのは全くの誤りです。
マイナス金利政策が金融機関の収益を悪化させ、金融システムを不安定にさせる、という副作用を各中央銀行が強く認識する中では、マイナス金利の幅をさらに拡大させることができる余地は、実際には限られるでしょう。
他方で、資産買い入れ策というもう一つの金融緩和手段については、ECBは国債の買い入れ増加額を段階的に縮小させ、2018年末にはネット買い入れ額(新規買い入れ額-償還額)をゼロとすることを決めました。日本銀行も、2016年9月以降、国債買い入れ増加額を着実に縮小させ続けてきました。中央銀行が、金融機関から大量に国債を買い入れ続ければ、それは市中での国債取引を停滞させ、流動性低下のリスクが高まるためです。
世界経済が後退に陥り、また金融市場が不安定になる際に、中央銀行が再び国債買い入れを増加させれば、流動性を極度に低下させることで国債市場に混乱を生じさせ、金融システムや経済をより不安定にさせてしまう可能性があります。中央銀行はこうしたリスクを十分に認識しているため、仮に景気後退が生じても国債買い入れを再び大幅に拡大させることには慎重でしょう。
米国でマイナス金利政策の導入は難しい
一方、米国では、政策金利に頭打ち感が広がってきました。FRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長が、政策金利は経済に中立的な水準に近づいてきた、との考えを示唆したことがきっかけです。過去1年間、FRBは年8回開かれるFOMC(米連邦公開市場委員会)で、1回おきに0.25%ずつの政策金利引き上げを着実に実施してきました。パウエル議長は、こうした安定的な政策姿勢が2019年も続くと決めつけることがないようにと、金融市場にあらかじめ注意を促したのです。
仮に、政策金利が3%程度で頭打ちとなる場合、米国でもマイナス金利政策を導入しない限りは、景気後退が生じた際の政策金利引き下げ余地が3%程度しかないことになります。これは、過去の9回の景気後退時の政策金利引き下げ幅の平均5.5%程度と比べて明らかに小さいものです。2007年の前回景気後退時には5.0%でした。
他方で、米国が日本やECBのように、マイナス金利政策を導入する可能性は限られます。その最大の障害となるのは、FRBが銀行に対してマイナスの当座預金金利を押し付ける権限を持っているか否か、という法的な問題です。連邦準備銀行法の条文では、「FRBは準備預金に対する金利を銀行に支払うことができる」とされているだけで、その金利をマイナスにする、つまり銀行がFRBに金利を支払うことが認められるか否かは明確でありません。
主要国の中で最も金融政策の正常化が進んでいる米国でさえも、このように、次の景気後退の際に金融緩和で対応できる余地はかなり小さい状況です。日本や欧州など他の主要国についてはなおさらです。このように、主要国で景気後退時に金融緩和で対応できる余地が小さいことが、来年以降の世界経済の見通しを一段と厳しいものとしているのです。
木内登英の近著
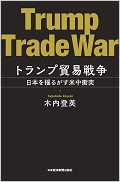
妥協なき報復合戦が自由貿易体制を突き崩す
- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。