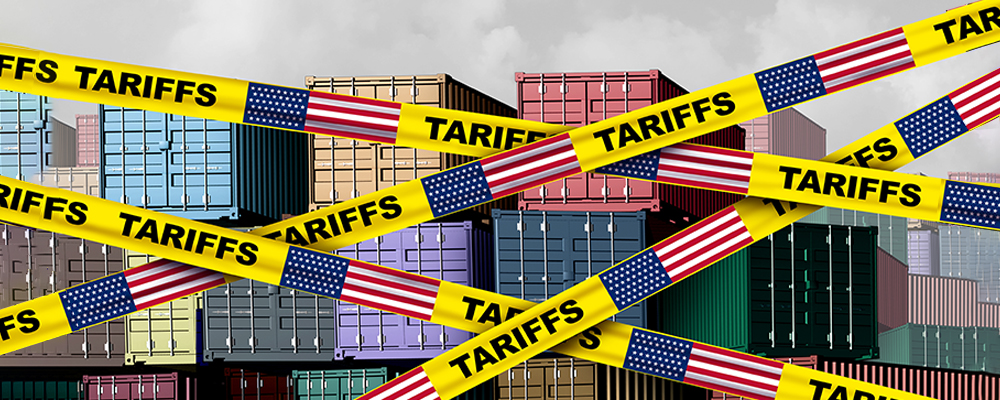
金融ITイノベーション事業本部 エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英
2025年2月1日にトランプ米大統領は、メキシコ、カナダからのほぼ全ての輸入品に25%の関税、中国からの輸入品に一律10%の追加関税を課す大統領令に署名しました。それには、相手国が米国に報復関税を課した際には、ペナルティーを強化する報復条項も含まれています。他方、米国経済への悪影響を和らげるため、カナダ産の石油や重要鉱物などについては税率を10%に抑える措置が講じられました。
1月20 日の第2次トランプ政権発足からわずか2週間足らずのうちに、この関税が発表されました。第1次トランプ政権では、政権2年目に追加関税が導入されたことを踏まえると、関税政策の優先度が第1次と比べて高まっていることがうかがえます。
トランプ関税の対象は日本へも
カナダ、メキシコ向け関税適用は1カ月延期も中国向け関税は発効
2025年2月4日の関税発効直前になって、メキシコ、カナダ向け関税の実施については、1カ月間延期されました。メキシコには、米国側が求めてきた合成麻薬フェンタニルや不法移民の流入対策として1万人の警備隊を配置すること、カナダにも約1万人の警備隊を配備して国境管理を強化すること、フェンタニル対策の責任者を任命することなどを条件に、米国は両国への関税適用を1カ月延期することを決めたのです。
他方、中国については予定通りに4日に関税が発効しました。これに対して中国は、即座に米国への報復措置を発表しています。米国からの石炭と液化天然ガス(LNG)に15%の関税、原油、農業機械、ピックアップトラック、大型エンジン車には10%の関税を課したのです。これを2月10日に発効しました。
さらにトランプ政権は2月20日に、全ての国を対象にして、鉄鋼・アルミニウム輸入品に25%の関税を課す、と発表し、3月12日に発効します。トランプ大統領は第1次政権下の2018年に、日本を含む主要国・地域から輸入される鉄鋼に25%、アルミニウムに10%の関税を課しましたが、実際には適用除外措置が多かったことから、今回は、それらを廃止して関税の実効性を高める狙いがあります。
トランプ政権の関税策はさらに続く見通しです。トランプ大統領は2月18日頃に、半導体、原油、天然ガスなどに関税を課す考えを明らかにしています。選挙時に主張していた全ての国に対して一律関税を課すことも、引き続き検討しています。その適用の発表時期については、必要な商務省や米国通商代表部(USTR)などの各官庁調査が終えた4月以降になる可能性があります。
他方、中国については予定通りに4日に関税が発効しました。これに対して中国は、即座に米国への報復措置を発表しています。米国からの石炭と液化天然ガス(LNG)に15%の関税、原油、農業機械、ピックアップトラック、大型エンジン車には10%の関税を課したのです。これを2月10日に発効しました。
さらにトランプ政権は2月20日に、全ての国を対象にして、鉄鋼・アルミニウム輸入品に25%の関税を課す、と発表し、3月12日に発効します。トランプ大統領は第1次政権下の2018年に、日本を含む主要国・地域から輸入される鉄鋼に25%、アルミニウムに10%の関税を課しましたが、実際には適用除外措置が多かったことから、今回は、それらを廃止して関税の実効性を高める狙いがあります。
トランプ政権の関税策はさらに続く見通しです。トランプ大統領は2月18日頃に、半導体、原油、天然ガスなどに関税を課す考えを明らかにしています。選挙時に主張していた全ての国に対して一律関税を課すことも、引き続き検討しています。その適用の発表時期については、必要な商務省や米国通商代表部(USTR)などの各官庁調査が終えた4月以降になる可能性があります。
本丸は貿易赤字削減で日本も一律関税の対象になる可能性
トランプ大統領がメキシコ、カナダ、中国への関税適用を決めたのは、合成麻薬フェンタニルと不法移民の流入についての対策が不十分であることへの制裁でした。ただし、これは半ば口実と言えるでしょう。
トランプ大統領は、米国の貿易赤字に強い不満を持っています。トランプ大統領にとって貿易赤字は、貿易相手国による不当な策略によって米国に損失が生じている状態であり、それを解消すればその分米国のGDPが拡大して米国経済をより強くできる、と考えていると見られます。それは、トランプ大統領のビジネスマンとしての感覚に基づく認識と思われますが、経済学的には正しくないでしょう。
追加関税で輸入を抑制しようとすれば、関税分だけ米国への輸入品が割高になります。その関税を支払うのは米国の輸入業者で、最終的には米国の個人や企業の負担になります。追加関税は米国内での増税策に他ならず、それは米国の個人消費など需要を悪化させてしまいます。
ところで、2024年の米国の輸入額の上位3カ国は、順にメキシコ、中国、カナダです。中国は米国の貿易赤字国の第1位でもあります。トランプ大統領がまずこの3カ国から関税適用を始めたのは、貿易赤字を削減する狙いもあったと考えられます。
そして日本は、2024年の米国の輸入額で第5位、貿易赤字額で第7位といずれも上位国です。トランプ大統領が、貿易赤字の削減を進めることを狙って、いずれ日本も本格的な関税の対象となる可能性はあります。
2月7日にワシントンで開かれた日米首脳会談後の記者会見でトランプ大統領は、会談では対日関税について「あまり議論しなかった」と話しました。しかし会談の冒頭では、対日貿易赤字を問題視しており、両国間の貿易収支を「平等」にしたいと発言していました。さらにこれが実現しなければ関税をかける考えがあることも示唆していました。特に自動車への関税については、「いつも選択肢としてある」と明言したのです。
この先、トランプ大統領が貿易赤字の削減を狙って全ての国、あるいは多くの国からの輸入品に一律関税を課す場合に、日本も対象になる可能性があります。また、日本からの輸入額全体の3割弱を占める自動車に関税を課す可能性も残されているでしょう。
トランプ大統領は、米国の貿易赤字に強い不満を持っています。トランプ大統領にとって貿易赤字は、貿易相手国による不当な策略によって米国に損失が生じている状態であり、それを解消すればその分米国のGDPが拡大して米国経済をより強くできる、と考えていると見られます。それは、トランプ大統領のビジネスマンとしての感覚に基づく認識と思われますが、経済学的には正しくないでしょう。
追加関税で輸入を抑制しようとすれば、関税分だけ米国への輸入品が割高になります。その関税を支払うのは米国の輸入業者で、最終的には米国の個人や企業の負担になります。追加関税は米国内での増税策に他ならず、それは米国の個人消費など需要を悪化させてしまいます。
ところで、2024年の米国の輸入額の上位3カ国は、順にメキシコ、中国、カナダです。中国は米国の貿易赤字国の第1位でもあります。トランプ大統領がまずこの3カ国から関税適用を始めたのは、貿易赤字を削減する狙いもあったと考えられます。
そして日本は、2024年の米国の輸入額で第5位、貿易赤字額で第7位といずれも上位国です。トランプ大統領が、貿易赤字の削減を進めることを狙って、いずれ日本も本格的な関税の対象となる可能性はあります。
2月7日にワシントンで開かれた日米首脳会談後の記者会見でトランプ大統領は、会談では対日関税について「あまり議論しなかった」と話しました。しかし会談の冒頭では、対日貿易赤字を問題視しており、両国間の貿易収支を「平等」にしたいと発言していました。さらにこれが実現しなければ関税をかける考えがあることも示唆していました。特に自動車への関税については、「いつも選択肢としてある」と明言したのです。
この先、トランプ大統領が貿易赤字の削減を狙って全ての国、あるいは多くの国からの輸入品に一律関税を課す場合に、日本も対象になる可能性があります。また、日本からの輸入額全体の3割弱を占める自動車に関税を課す可能性も残されているでしょう。
トランプ関税に3つの壁
国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠にする初の追加関税
今後のトランプ政権の関税政策を考えるうえで注目しておきたいのは、メキシコ、カナダ、中国への関税適用を決めた際に、国際緊急経済権限法(IEEPA:INTERNATIONAL EMERGENCY ECONOMIC POWERS ACT)を根拠にしたことです。
国際緊急経済権限法(IEEPA)は、米国の安全保障、外交政策、経済に対する異例かつ重大な脅威を受けて大統領が緊急事態を宣言した場合、大統領にそれに対処する権限を与えるものです。過去にはテロ組織、テロ国などに対して多く適用されてきました。IEEPAに基づいて大統領が追加関税を課したことは、今回が始めてです。
第1次トランプ政権が追加関税を導入した際にその法的根拠としたのは、通商法232条と通商法301条でした。通商法232条は、ある製品の輸入が米国の安全保障を損なう恐れがあると商務省が判断した際に、それを是正するための措置をとる権利を大統領に与えています。また、通商法301条は、外国の貿易慣行が不合理、差別的である場合、大統領の指示に従って米国通商代表部(USTR)に輸入制限措置を発動する権利を与えています。
しかし、今回のケースでは、この2つの通商法を根拠に関税を課することは難しかったのではないかと考えられます。合成麻薬フェンタニルと不法移民の流入が、米国の安全保障を脅かすリスクがあること、あるいはそれらが貿易相手国の貿易慣行が不正であることによるものとを説明するのは、かなり無理があるためです。
さらに、通商法に基づいて全ての輸入品に一律関税を課す場合は、第1次トランプ政権が導入した個別品目への関税の場合と比べて、格段に大きな事務負担が生じます。通商法232条、通商法301条はともに、追加関税措置を講じる前に調査を行うことが求められます。通商法232条では商務省による270日以内の調査、通商法301条のもとではUSTR(米通商代表部)による12カ月以内の調査が必要となります。
「法律の壁」とも言える、こうした状況から、今回トランプ政権は、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に3カ国に一律関税を課すことを決めたものと推察されます。
国際緊急経済権限法(IEEPA)は、米国の安全保障、外交政策、経済に対する異例かつ重大な脅威を受けて大統領が緊急事態を宣言した場合、大統領にそれに対処する権限を与えるものです。過去にはテロ組織、テロ国などに対して多く適用されてきました。IEEPAに基づいて大統領が追加関税を課したことは、今回が始めてです。
第1次トランプ政権が追加関税を導入した際にその法的根拠としたのは、通商法232条と通商法301条でした。通商法232条は、ある製品の輸入が米国の安全保障を損なう恐れがあると商務省が判断した際に、それを是正するための措置をとる権利を大統領に与えています。また、通商法301条は、外国の貿易慣行が不合理、差別的である場合、大統領の指示に従って米国通商代表部(USTR)に輸入制限措置を発動する権利を与えています。
しかし、今回のケースでは、この2つの通商法を根拠に関税を課することは難しかったのではないかと考えられます。合成麻薬フェンタニルと不法移民の流入が、米国の安全保障を脅かすリスクがあること、あるいはそれらが貿易相手国の貿易慣行が不正であることによるものとを説明するのは、かなり無理があるためです。
さらに、通商法に基づいて全ての輸入品に一律関税を課す場合は、第1次トランプ政権が導入した個別品目への関税の場合と比べて、格段に大きな事務負担が生じます。通商法232条、通商法301条はともに、追加関税措置を講じる前に調査を行うことが求められます。通商法232条では商務省による270日以内の調査、通商法301条のもとではUSTR(米通商代表部)による12カ月以内の調査が必要となります。
「法律の壁」とも言える、こうした状況から、今回トランプ政権は、国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に3カ国に一律関税を課すことを決めたものと推察されます。
国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠にする一律関税の拡大にも障害
今後、一律関税の対象国を広げていく際には、この国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠にすることが予想されます。しかしそれにも問題はあるのです。
国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき大統領がその権限を行使する前には、議会との協議が義務付けられています。追加関税を発動する際には、その背景や必要性などについて事前に議会に報告することも義務付けられています。この過程で、議会が追加関税に反対し、追加関税の導入を阻まれてしまう可能性があるでしょう。
また同法の下では、実施後に少なくとも6カ月に1回は、講じた措置について議会に報告しなければならない点も、トランプ政権が一律関税を課すことの制約となるでしょう。
また、貿易赤字の拡大などを経済緊急事態であると宣言して、全ての国、あるいは多くの国に一律追加関税を課すことはさすがに無理があります。その点は、議会も疑問視することでしょう。一律追加関税を実行するためには、このような「議会の壁」も乗り越える必要があるのです。
国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき大統領がその権限を行使する前には、議会との協議が義務付けられています。追加関税を発動する際には、その背景や必要性などについて事前に議会に報告することも義務付けられています。この過程で、議会が追加関税に反対し、追加関税の導入を阻まれてしまう可能性があるでしょう。
また同法の下では、実施後に少なくとも6カ月に1回は、講じた措置について議会に報告しなければならない点も、トランプ政権が一律関税を課すことの制約となるでしょう。
また、貿易赤字の拡大などを経済緊急事態であると宣言して、全ての国、あるいは多くの国に一律追加関税を課すことはさすがに無理があります。その点は、議会も疑問視することでしょう。一律追加関税を実行するためには、このような「議会の壁」も乗り越える必要があるのです。
トランプ政権が目指す一律追加関税の拡大には「3つの壁」
このような点を踏まえると、トランプ政権が大統領選挙で掲げていた、全ての国からの輸入品に一律10%~20%の関税を課すことには、まず、法律の壁が立ちはだかると言えます。仮に通商法を根拠にする場合でも、全ての輸入品に対して、一律に国家の安全保障を脅かすリスクがある、あるいは不公正貿易が行われていることを理由とするのは無理があります。また、事前調査などの膨大な事務負担もその障害となるでしょう。
さらに、追加関税は、輸入される部品、材料、原料、製品の価格を高めるという点で、企業や国民の不満を招く恐れがあります。実際、トランプ政権が2月1日に3カ国に対して関税を適用することを発表した際には、全米小売業協会(NRF)、全米石油協会(API)、全米鉄鋼労働組合(USW)などが、それに強い反発を示しました。また、サウスカロライナ州選出の上院共和党議員ティム・スコット氏は、「関税はサウスカロライナ州の住民に対する増税以外の何物でもない」として、トランプ氏の関税措置を強く批判しています。
追加関税による物価高がより顕著になれば、国民の間でバイデン前政権に代わってトランプ政権が物価を安定させてくれるとの期待が失望に変わり、このことが「世論の壁」となって、2026年の中間選挙で共和党に逆風が吹く可能性があるでしょう。
このように、トランプ政権が目指す一律追加関税の拡大には、「法律の壁」、「議会の壁」、「世論の壁」、の「3つの壁」が障害になるものと考えられます。そのため、一律追加関税の拡大は、トランプ大統領が大統領選挙中に打ち出したものよりも限定されたものに収まることが考えられます。
それでも、どの程度限定されるのかについては依然としてかなり不確実です。一律追加関税による世界経済、米国経済、日本経済への悪影響が相応に生じる事態は、やはり避けられないのではないでしょうか。
さらに、追加関税は、輸入される部品、材料、原料、製品の価格を高めるという点で、企業や国民の不満を招く恐れがあります。実際、トランプ政権が2月1日に3カ国に対して関税を適用することを発表した際には、全米小売業協会(NRF)、全米石油協会(API)、全米鉄鋼労働組合(USW)などが、それに強い反発を示しました。また、サウスカロライナ州選出の上院共和党議員ティム・スコット氏は、「関税はサウスカロライナ州の住民に対する増税以外の何物でもない」として、トランプ氏の関税措置を強く批判しています。
追加関税による物価高がより顕著になれば、国民の間でバイデン前政権に代わってトランプ政権が物価を安定させてくれるとの期待が失望に変わり、このことが「世論の壁」となって、2026年の中間選挙で共和党に逆風が吹く可能性があるでしょう。
このように、トランプ政権が目指す一律追加関税の拡大には、「法律の壁」、「議会の壁」、「世論の壁」、の「3つの壁」が障害になるものと考えられます。そのため、一律追加関税の拡大は、トランプ大統領が大統領選挙中に打ち出したものよりも限定されたものに収まることが考えられます。
それでも、どの程度限定されるのかについては依然としてかなり不確実です。一律追加関税による世界経済、米国経済、日本経済への悪影響が相応に生じる事態は、やはり避けられないのではないでしょうか。
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。