「事実上の正常化」は既に相当進められてきた
政府は日本銀行の新たな正副総裁の人事案を、2月14日に国会に提示する。新総裁の最優先課題は、実現が難しい2%の物価目標と強く結びついた硬直的な金融政策を柔軟化、正常化することだ。いわば出口戦略である。
金融緩和に積極的な黒田総裁のもとでさえ、事務方主導で「事実上の正常化」が進められてきたことを踏まえれば、誰が新総裁になってもその流れが続く可能性は高いだろう。事務方の影響力は大きいのである。さらに、今までの「事実上の正常化」から、明確に政策の転換を宣言したうえでの「明示的な正常化」へと変わることで、正常化はより加速されるはずだ。
「事実上の正常化」とは、異例の金融緩和の修正や後退ではないと対外的には説明しつつも、実際には金融緩和に伴う副作用を軽減し、政策の柔軟化を進める措置を実施することだ。
かつては年間80兆円の国債買いれ増額を実施していたが、その後買い入れ額を大幅に削減したこと、もはやETFをほとんど買い入れていないこと、昨年12月の利回り変動幅の上限引き上げを含め、イールドカーブ・コントロール(YCC)の変動幅を段階的に拡大してきたこと、特別付利制度などを通じて、マイナス金利政策による銀行の負担を軽減してきたこと、などが「事実上の正常化」にあたる。
異例の金融緩和の効果は小さい
10年間続いた異例の金融緩和のもとでも、金利の低下幅は限られた。短期金利は緩和開始前の+0.1%から現在の-0.1%へと、わずか0.2%低下したに過ぎない。10年国債利回りは緩和開始前の+0.8%から一時小幅マイナスとなったが、現在は+0.5%程度である。低下幅はわずか0.3%程度だ。
この10年間、日本銀行は様々な政策を打ち出してきたが、政策効果が確実に期待できるのは金利の変化のみと言えるだろう。国債、ETFの買い入れなど量的な政策の効果は不確実である。
金利を下げることで、現在と将来の需要の配分を変化させ、将来の需要を前借りするというのが、金融緩和効果の本質だ。金利低下幅がわずかであれば、その効果は限られてしまう。異例の金融緩和は、既に金利の低下余地がかなり小さい環境で始められたため、その効果を発揮するのはそもそも難しかったのである。
日本銀行が10年前の異例の金融緩和を実施した後も、潜在成長率、労働生産性上昇率は低下傾向を続けた(図表)。足元では一時的に上昇しているとはいえ、両者の影響を受けやすい賃金上昇率と物価上昇率もやはり低下トレンドを辿ってきた。異例の金融緩和に、それを転換させるほどの力はなかったのである。
図表 潜在成長率
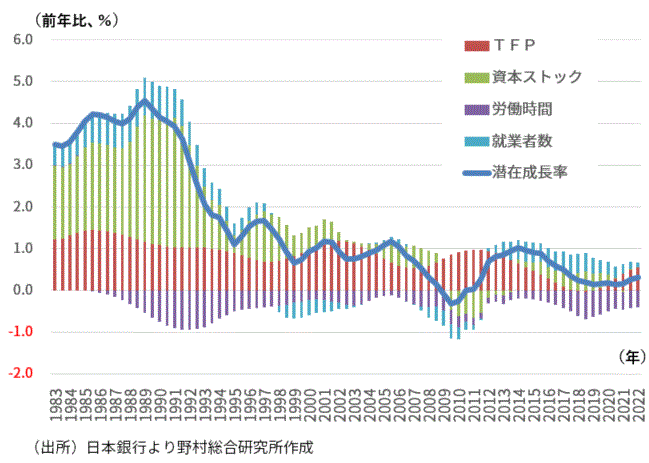
増大を続けた副作用
他方で、異例の金融緩和は既に顕在化しているもの、今後顕在化してくるものを含め、様々な副作用のリスクを高めた。昨年来の円安加速、国債市場の混乱はその一端であるが、市場の流動性低下など市場機能の低下、金融機関の収益圧迫、日本銀行のバランスシートの悪化などが挙げられる。
さらに、異例の金融緩和を実施することで、日本経済の再生にとって欠かせない経済の潜在力向上に資する政府の成長戦略、構造改革を阻害してしまった面があるのではないか。また、異例の金融緩和が財政の規律を低下させ、過去10年間に進んだ政府債務の増大が、将来の需要見通しを悪化させることを通じて、日本経済の潜在力を低下させてしまった面もあるだろう。
異例の金融緩和は副作用が効果を上回り修正が必要に
金融政策は「効果と副作用の比較衡量」に基づいて慎重に進めていくのが本道である。効果が小さい一方、将来にわたって副作用が大きい現在の金融緩和を見直し、正常化していく必要がある。そのうえで、柔軟に短期金利を調整することや銀行に対する資金供給量を調整するという、伝統的な金融政策手法に戻していくことが重要だ。
新たな総裁の下で日本銀行が最初に着手するのは、第1にYCCの大幅な見直しであり、利回り変動の再拡大や変動幅の撤廃などが考えられる(コラム「 新総裁の下で日銀が最初に着手するのはYCC改革か 」、2023年2月9日)。
第2に、2%の物価目標を中長期の目標などに修正することで、柔軟な金融政策を取り戻し、正常化を進める環境を整えることだ。
第3が、マイナス金利解除、YCC撤廃と考えられるが、その実施は、経済・金融面での環境が整った後であり、2024年半ば以降と考えられる。その後に、保有国債残高の削減など量的引き締め策、ETFのオフバランス化などが、数年かけて進められるのではないかと予想される。
日本銀行は金融市場、金融機関への影響に配慮して政策修正を慎重に進める
このような正常化の過程では、利回り上昇や円高進行などが生じ、金融機関の財務や経済に打撃を与えてしまう可能性がある。しかし新体制の日本銀行は、伝統的な金融政策姿勢に基づいて、金融機関の財務や経済に与える影響に十分注意を払いながら、慎重に正常化を進めていくだろう。
正常化の過程で金融機関の財務や経済に大きな打撃が及ぶリスクよりも、そのリスクに配慮して日本銀行の正常化のスピードがかなり緩やかになってしまうことを心配すべきだろう。
そして、金融政策の正常化とともに、日本銀行のコミュニケーションの正常化も同時に進めていくことが、日本銀行が金融市場や国民からの信頼を取り戻すために必要となる(コラム「 日銀次期総裁に求められる金融政策とコミュニケーションの同時正常化 」、2023年2月6日)。
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。