
木内登英の経済の潮流――「2020年の経済のリスクは米中貿易摩擦から中東情勢へ」
米国と中国の両政府は、間もなく貿易協議の部分合意に署名する予定です。米中貿易摩擦の緩和は、内外経済の下振れリスクを低下させます。これに代わって、年明け直後に新たなリスクとして浮上してきたのが、中東情勢の緊迫化です。
にわかに高まった中東情勢の緊迫化
年明けと共に、中東情勢は一気に緊迫の度合いを増しています。米国政府は1月2日(米国時間)にイラクの首都バグダッドにロケット弾攻撃を行いました。これにより、イラン革命防衛隊の精鋭部隊「コッズ部隊」のソレイマニ司令官を含む少なくとも8人が死亡しました。
革命防衛隊はイランの最高指導者であるハメネイ師の直属組織で、コッズ部隊はその中核を占め、イランの対外工作を取り仕切る重要組織です。また、ソレイマニ司令官は、イラン国民から英雄視されてきた人物です。イランは、今回の事件を受けて米国への報復を即座に明言し、実際1月8日(日本時間)に、イラクの米軍駐留基地を攻撃しました。
ソレイマニ氏の殺害は、トランプ米大統領によるイラン核合意の破棄以降高まっていた米国とイランとの間の対立を決定的にするばかりでなく、中東地域全体の地政学リスクを一気に高めることにもなり得ます。トランプ政権は、イランによるイラクの米軍駐留基地攻撃を受けて、イランへの経済制裁を強化することを決めた一方、軍事的な報復は今のところ控えています。しかし今後の情勢は不透明で、両国間の対立が、制御不能の軍事衝突に陥るリスクも出てきたと見るべきでしょう。
トランプ大統領は、イラクやアフガニスタンからの駐留米軍の撤収を公約に掲げてきました。しかし、この公約を覆して、中東地域での軍事活動を活発化させる可能性も出てきました。今年の米国大統領選挙を意識し、海外での軍事的な活動の活発化を通じて、国内で大きな逆風となっているウクライナ疑惑の弾劾裁判から国民の目を国外にそらすことを狙う戦略をとる可能性があるためです。この点から、今回の事件が、米国大統領選挙の年の初めに起こったことは、偶然ではないように思います。
中東情勢悪化で日本経済に3つの逆風
昨年末から年明けにかけて世界の金融市場は、米中貿易摩擦の緊張緩和や世界経済の安定化への期待から、楽観の度合いをかなり強めていました。中東情勢の緊迫化は、こうした金融市場の楽観論に水を差すものとなりました。
そして今回の事件は、2020年の金融市場にとって、リスクの重心が、米中貿易摩擦、世界経済の失速懸念などから、米大統領選挙とも結びついた地政学リスクへとシフトしていることを示唆している面があります。
世界経済は米国、中国を中心に安定化の兆しを見せており、国内経済も今後はその恩恵を受けて緩やかに持ち直す姿が展望されます。しかし、米国とイランとの間で軍事的対立がさらにエスカレートし、原油価格が大幅に上昇する場合には、それらが内外経済の持ち直し傾向の障害となる可能性が生じ得ます。
内閣府の短期日本経済計量モデル(2018年版)によると、原油価格の10%の上昇は、国内GDPを2年間で0.1%程度押し下げます。この程度であれば国内経済が受ける打撃は必ずしも深刻ではありませんが、中東地域での地政学リスクが高まり、原油価格が上昇する局面では、同時に円高が生じやすくなります。
仮に対ドルで5%円高が進めば、GDPは2年間で0.3%程度も押し下げられる計算となります。さらに円高進行は、株安も誘発する可能性が高いでしょう。このように、中東情勢を受けて原油高、円高、株安の3つの逆風が同時に強まれば、国内経済の安定が大きく揺るがされることも考えられるところです。
現状では、中東情勢の悪化が国内経済を一気に失速させると考えるのは悲観的過ぎるでしょうが、国内経済や金融市場にとって大きな不確定要素が年初に一気に浮上したことは間違いありません。
(2020年1月8日執筆)
木内登英の近著
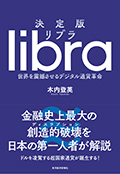
世界を震撼させるデジタル通貨革命
- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。