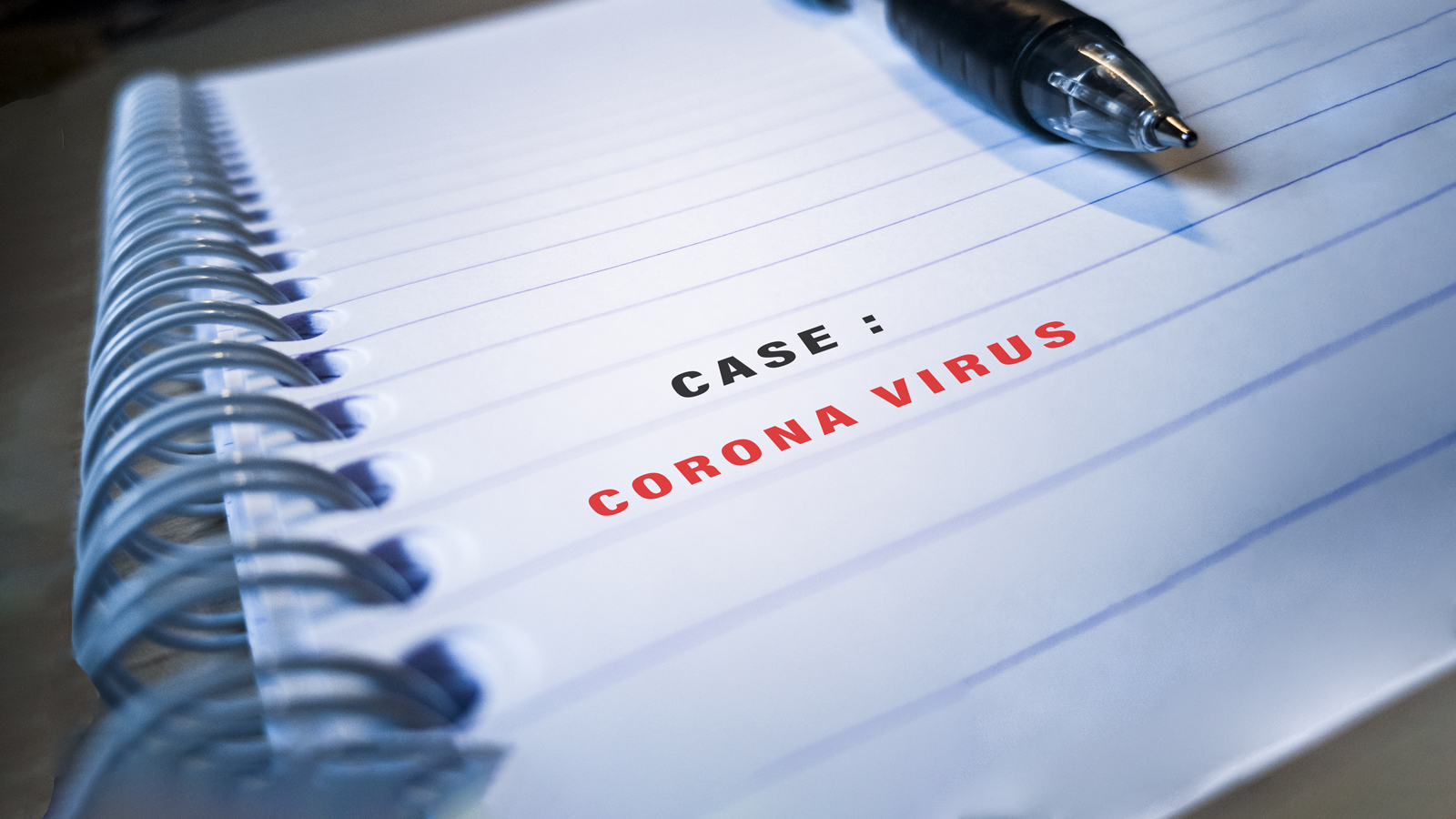
木内登英の経済の潮流――「新型コロナウイルスが世界の金融市場を揺るがす」
新型コロナウイルスの感染拡大は、発生源となった中国ではその勢いに衰えが見られ始めています。しかし、その他の地域ではなお拡大傾向が続き、終息の兆しは見えてきません。そうした中、経済の先行き不安から、世界の金融市場は大きく動揺しています。
FRBの緊急利下げが裏目に出た感も
昨年見られた主要国での金融緩和の流れは一巡した、と見る向きが最近までは優勢でした。しかし新型コロナウイルスへの対応策として、3月3日にFRB(米連邦準備制度理事会)が0.5%の大幅な利下げ(政策金利引下げ)に踏み切ると、世界はにわかに金融緩和モードへと戻ってしまいました。
市場の利下げ観測に先手を打つ形で実施された、いわばサプライズを狙ったFRBの緊急利下げでしたが、当日の米国株価は大幅に下落しました。またこれをきっかけに、世界の金融市場はむしろ混迷の度を深めたように思います。サプライズ戦略は、裏目に出てしまったのです。
それは、「新型肺炎による経済、金融への影響はそれほどまでに深刻なのか」、といった市場の疑心暗鬼をむしろ強めてしまったからではないでしょうか。このことは、2016年1月に、日本銀行がマイナス金利政策の導入を突如発表した際に、円高・株安が進むなど、金融市場が予想外に悪く反応したことを彷彿とさせます。
米国の10年国債利回りは歴史的水準まで低下
FRBの緊急利下げが金融市場をむしろ動揺させてしまった背景には、米国でゼロ近傍の金利環境が常態化してしまう、との懸念がにわかに浮上したこともあったと思います。
米国の10年国債利回りは、緊急利下げの直後に1.0%の水準を割り込み、その後、一時は0.3%台まで急低下しました。これは、過去に遡っても見つけることのできない、まさに歴史的低水準です。
向こう数か月のうちに米国の政策金利は、現状の1.0%~1.25%の水準から、ゼロ近くまで引き下げられるとの予想が、金融市場に織り込まれています。仮にこうした金融緩和策が十分な効果を発揮すると市場が考えれば、いずれ景気は改善し物価上昇率も高まるため、政策金利も引き上げられていくという見通しとなります。しかしその場合、10年国債利回りはこのような低い水準にはならないはずです。
低金利環境が長期化する中、米国での金融緩和の効果は従来に比べてかなり低下した、と金融市場は認識しているのだと思われます。その場合、金融緩和を実施しても経済、物価の低迷は長く続くことから、政策金利はゼロ近傍の状態をなかなか脱することができません。そうした将来像を金融市場が展望する時に、10年国債利回りはこのような歴史的低水準となるのです。
米国も日本と欧州の状況に近づく
低金利環境が長期化すると、金融機関の収益は悪化し、金融仲介機能が損なわれることで、経済の潜在力は削がれてしまいます。また、これが低金利環境をさらに長期化させるという形で、悪循環が生じる可能性があります。こうしたメカニズムは、まさに日本が過去に経験してきたことです。
米国も、日本や欧州と同様に、ゼロ金利が常態化する経済・金融環境となってしまった可能性がある。少なくとも金融市場は、緊急利下げをきっかけにして、そうしたリスクを強く意識し始めたのではないでしょうか。
仮にそうした市場の見方が正しいとすれば、世界経済をけん引していた米国経済の影響力は徐々に低下していき、また、何らかのショックがあった際にも、世界経済は今までのように、米国の金融緩和に助けてもらうことが難しくなっていくでしょう。
新型コロナウイルスの感染拡大、それを受けた緊急利下げをきっかけにして、金融市場はこのようなかなり厳しい将来展望をにわかに抱くようになったと言えるでしょう。
木内登英の近著
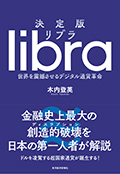
世界を震撼させるデジタル通貨革命
- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。