
木内登英の経済の潮流――「緊急事態宣言の延長で追加財政支援の必要額が増大」
政府は、5月6日に期限を迎えた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言を、5月31日まで延長しました。その結果、不要不急の消費がさらに控えられ、個人消費は追加で11.2兆円減少、2020年のGDPは追加で2.0%低下する計算となります。
半年間で47兆円規模の個人消費が消失か
緊急事態宣言が始まった4月7日以降の合計でみると、個人消費は25.1兆円減少し、2020年のGDPは4.5%低下する計算となります。
さらに、6月から9月にかけては規制措置が段階的に緩和されていくとの前提で試算すると、4月から9月までの半年間で消費は47.0兆円減少し、GDPは8.5%低下することになります
※
。
新型コロナウイルスで打撃を受けた企業の経費部分を支援する、というのが、政府の企業支援の基本的な考え方だと思われます。それを通じて、企業の事業活動が継続され、また労働者が生活を維持できるようにすることが、支援策の狙いです。
上記の試算に従って半年間で個人消費が47.0兆円減少する場合、その金額から半年間での経常利益の減少額4.1兆円(推定)を除いた42.9兆円が、新型コロナウイルスで打撃を受けた、個人消費関連を中心とする企業への支援の必要額となります。その中では、雇用調整助成金や個人向け給付金を通じた人件費部分の支援、家賃の支援が大部分を占めます。
追加で32.3兆円の財政支出が必要に
ところで、先日成立した総額26.5兆円の2020年度補正予算では、企業と労働者を支援する「雇用の維持と事業の継続」に、19.5兆円が計上されました。ただしこのうち、1人当たり一律10万円の給付金制度には、新型コロナウイルスで打撃を受けなかった個人にも多く支給され、その多くが貯蓄に回される、という問題があります。
そこで、打撃を受けた世帯に支給されることが政府の補正予算案に当初盛り込まれていた、1世帯当たり最大30万円の給付金の総額に相当する分が、実際には打撃を受けた個人の手に届くものと仮定すると、実質的な企業、個人への支援金額は10.6兆円となります。
既に計算した42.9兆円から、この10.6兆円を引いた32.3兆円が、企業と個人を支援するために必要となる、追加の財政支出額となるのです。
家賃支援だけでも追加で4.8兆円が必要に
緊急事態宣言の延長を受け、間髪を入れずに、第2次補正予算の議論が活発となる可能性が高い状況です。
その際、大きな焦点となるのは、雇用調整助成金の上限引き上げ、学生支援と並んで、企業の家賃(賃貸料)の支援となります。
新型コロナウイルスで打撃を受ける企業の売上高に占める家賃支払いの比率が、飲食店の平均とされる約10%とし、それに基づいて、売上高の減少分の1割の家賃支払いが滞る、と仮定してみましょう。半年間で個人消費が47.0兆円減少すると、中間投入も含めた企業の売上高(生産額)は、70.6兆円減少する計算となります(内閣府の2017年産業連関表によると、個人消費が1単位減少すると、企業の生産額は1.503(生産誘発係数)単位減少する)。
企業の売上高が70.6兆円減少すると、その1割の7.1兆円の家賃支援が必要となります。政府は、補正予算に計上した企業向けの持続化給付金2.3兆円は、家賃支援を主に念頭に置いたもの、と説明しています。その場合、家賃支援部分だけでも、半年間で両者の差である4.8兆円の追加の財政支出が必要となる計算です。
追加の財政支出は不可避も財源確保は重要
いずれにしても、今回の補正予算だけでは、企業の経営や個人の生活を支えるためには、明らかに十分ではないと考えられます。今後、複数回に渡る補正予算編成は不可避でしょう。
ただし、追加の財政支出を実施する際に、安易に赤字国債の発行で資金を調達することは問題ではないでしょうか。赤字国債の発行拡大は、将来世代の負担を高め、それを通じて日本経済の将来展望をより悪化させることにもなります。
こうした国難に際しては、同世代が痛みを分かち合い、新型コロナウイルス問題で大きな打撃を受けた人や企業を、打撃が小さい人や企業、あるいは資金面で余裕のある人や企業が支えることが重要だと思います。
今後の補正予算編成では、政府は、今回の補正予算のように安易に赤字国債の発行にその財源を頼るのではなく、近い将来の増収策といった形で財源をしっかりと確保した上で、必要な追加の財政支援策を講じてほしいと思います。
- コラム「 緊急事態宣言は延長:半年間で50兆円規模の個人消費が消失か 」(2020年4月30日)を参照
木内登英の近著
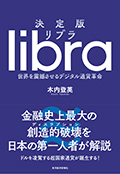
世界を震撼させるデジタル通貨革命
- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。