
木内登英の経済の潮流――「2021年は攻めの経済政策への転換に期待」
年初に突如浮上した新型コロナウイルス問題の解決に、未だ十分な目途が立たない状況のまま世界は年を越すことになります。2021年もその後遺症は経済・社会活動に色濃く残ることになるでしょう。そうした中、各国の経済政策が、ポストコロナを睨んで大きく転換していくことを期待したいと思います。
消費者の行動変容が産業構造を変える
コロナショックで大きな打撃を受けた企業と労働者を、特別な融資制度、給付金制度などを通じて積極的に支援する措置を、各国政府は講じてきました。これはコロナショックの痛みを和らげるとともに、企業が現在のビジネスを継続し、また労働者が現在の企業で働き続けることを助けるものです。
足もとでは、多くの国で感染の再拡大傾向が見られ、その影響から、欧州に続いて日本や米国でも、来年初めにかけて成長率が再びマイナスとなる、「景気二番底」のリスクが燻っています。
他方、ワクチン接種の広がりなどを背景に、来年後半にかけて感染リスクは徐々に低下していき、それが各国での経済活動の正常化を後押しする、と考えられます。それでも、感染リスクへの警戒は定着することなどから、旅行、飲食、アミューズメント関連などへの消費者の支出は従来よりも選別され、全体の支出水準はコロナショック前まで容易には戻らないでしょう。いわゆる行動変容が生じるのですが、これこそが産業構造の転換を促す原動力となります。
産業構造の転換を促す「攻め」の政策への転換を
来年には、消費者の選別が進むことによって、顧客が戻ってくる企業と十分に戻らない企業との間の優劣、競争力の差が次第に明確になっていくでしょう。競争力を失った企業を国費で支え続けることは、国民負担と経済の効率性の観点から、適切な政策ではなくなってきます。現時点では妥当な企業、労働者の支援策が、局面が異なってくれば、産業構造の転換を妨げ、経済の非効率な部分を温存させる後ろ向きの政策へとその位置付けが変わってしまうのです。
そこで政府には、競争力が低下した企業の業態転換と労働者の転職を支援する新たな政策へと、大きく転換することが求められます。いわばコロナショックを受けた「守り」の政策から、ポストコロナを見据えた「攻め」の政策への転換です。そうした政策が奏功し、産業構造の転換が促されれば、コロナショック後の経済の回復ペースも高まります。
中小企業の生産性向上策を同時に進める
ところで日本では、ポストコロナを見据えたこうした産業構造の転換と同時に、長年の課題である中小企業の生産性向上も、並行して進めていく取り組みが重要となるでしょう。
コロナショックで最も打撃を受けたのは、中小企業の比率が高い飲食、宿泊、小売、卸売業など流通・サービス業ですが、これらは国際比較で見ても日本の生産性が極めて低い業種です。仮にこの4業種の労働生産性が、米国の水準とのギャップの4分の1縮小させることができるだけで、独自の試算によると、日本経済全体の労働生産性は8.3%も押し上げられます。
中小企業全体の生産性を引き上げるには、既存の中小企業の生産性を引き上げる、生産性の高い中小企業の参入を促すことに加えて、生産性の高い中小企業の廃業を抑える、という政策もまた重要になるでしょう。後継者不足・不在によって、生産性の高い優良な中小企業が廃業を強いられるケースが少なくないためです。これは、日本経済にとって大きな損失と言えます。
コロナショックを逆手にとって日本経済の潜在力を高める
そこで、政府の成長戦略会議では、補助金制度などを活用して、コロナショックで打撃を受けた中小企業が業態転換を通じて生産性、競争力を向上させることを助ける方針に加えて、後継者問題を抱える中小企業を存続させるために、M&A(合併・買収)を強く支援する方針も、前面に打ち出されています。
政府は、中小企業のM&Aを税制面から促す措置も検討しています。企業買収後の想定外の損失に対応できるよう、買収費の一部を準備金として計上し、それを損金として算入できるようにする、買収後も雇用を維持し、給与を増加させることを支援するため、給与総額の増加分の一定割合を税控除する措置の導入などが検討されているのです。
企業の業態転換やM&Aが活発になれば、銀行にも新たなビジネス機会の拡大となります。各銀行は、後継者問題への対応からM&Aに既に積極的に取り組んでいますが、より広域での企業情報の共有が銀行間で進み、企業のマッチングがより多く達成されることを促すべく、民間の取組みに積極的に関与していく姿勢も、政府にはまた求められるのではないでしょうか。
ポストコロナを睨んで、消費者の新たな需要を取り込むための企業の業態転換が進み、また事業継承のためのM&Aが活発となり、結果として生産性向上を伴う形で産業構造の転換が円滑に進むことに大いに期待したいと思います。仮にそれが実現すれば、日本は「新型コロナウイルス問題を逆手にとって、より潜在力を高めることに成功した経済」として世界にアピールできるでしょう。
木内登英の近著
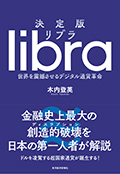
世界を震撼させるデジタル通貨革命
- NRIジャーナルの更新情報はFacebookページでもお知らせしています
プロフィール
-
木内 登英のポートレート 木内 登英
金融ITイノベーション事業本部
エグゼクティブ・エコノミスト
1987年に野村総合研究所に入社後、経済研究部・日本経済調査室(東京)に配属され、それ以降、エコノミストとして職歴を重ねた。1990年に野村総合研究所ドイツ(フランクフルト)、1996年には野村総合研究所アメリカ(ニューヨーク)で欧米の経済分析を担当。2004年に野村證券に転籍し、2007年に経済調査部長兼チーフエコノミストとして、グローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当。2012年に内閣の任命により、日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員に就任し、金融政策及びその他の業務を5年間担った。2017年7月より現職。
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。