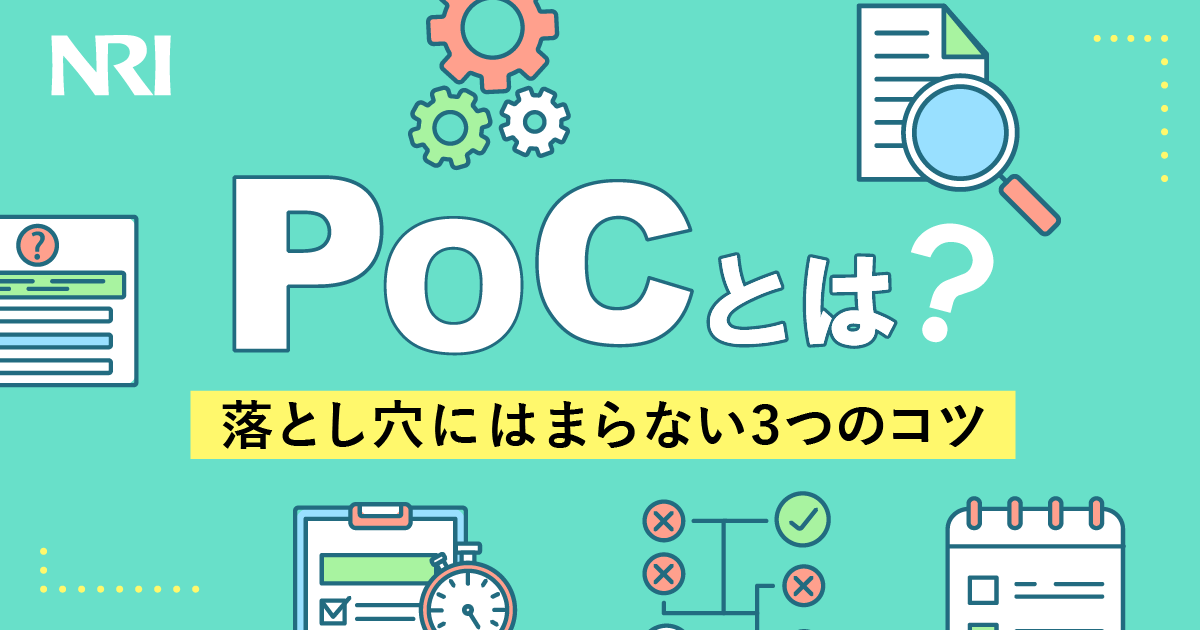
DX時代といわれる昨今では、新サービスの本格開発をする前に、その効果などを検証する目的でPoC(Proof of Concept=概念実証)を行う企業が一般的になっています。一方、「どのように進めていいのかわからない」という悩みもよく聞きます。ついには、落とし穴にはまって抜け出せない状態になり「途中で挫折してしまった」ことも少なくないようです。
そこで、本記事ではサービス開発の現場でPoC支援を行っているコンサルタントが、「新サービスを着実に市場投入まで導くための」現場で役立つ実践ノウハウを2回にわたりわかりやすく解説します。
執筆者プロフィール

武内 麻里亜:
2010年野村総合研究所(NRI)入社。専門領域は不動産業界を対象とした新サービス検討支援、システム化構想・計画の策定支援、業務改革、PMO支援。顧客企業に寄り添った支援を得意とする。
はじめに
こんにちは、野村総合研究所のシステムコンサルティング事業本部の武内です。前回は新サービスの検証の進め方について解説しました。今回は、新サービスの検討を支援してきた経験を踏まえて、PoCを上手く進めるためのコツをご紹介します。
PoCで陥りがちな“落とし穴”
PoCに時間や費用ばかりかかって、肝心の検証やサービス案の改善がうまく進まないことがあります。それはPoC特有の“落とし穴”にはまってしまっている可能性があります。今回は、PoCの途中で陥りがちな3つの落とし穴について説明します。
落とし穴1.サービス案に想い入れのないメンバーを選定してしまう
新サービス検討チームのメンバーをサービス案に関係なく決めてしまうことです。例えば、専門性や過去の人事評価だけで選んでしまうケースです。なぜそれが問題かというと、新サービスの検討には障害がつきものであり、それを乗り越えるには、メンバーの並々ならぬ熱意が必要だからです。
熱意は、専門性やスキルというより、そのサービスにどれだけ”想い入れ”があるかで決まります。いくら高い専門性をもっていたとしても、上から決まったサービスを用意され、割り振られたタスクを受動的にこなすだけでは想い入れを持つことは難しいです。そうしたメンバーで構成されたチームでは、活動がなかなか前に進みません。
落とし穴2.計画策定やプロトタイプ作りに注力しすぎてしまう
計画策定やプロトタイプ作りに時間や労力をかけすぎてしまうことです。
新サービスの検討では不確定要素が多いため、走りながら(PoCを行いながら)改善していくという考え方が必要ですが、既存サービスのやり方から抜け出せず、事前の計画立案に必要以上に手をかけてしまう場合があります。また、現場は正しく認識していても上層部の理解が足りず、綿密な計画を要求されるケースも少なくありません。
計画策定やプロトタイプ作りに時間や労力をかけすぎると活動費も膨らんで、大掛かりなプロジェクトになってしまいます。そうなると、社内調整にも多大な時間や労力を費やさざるを得ず、肝心のPoCやサービス検討にエネルギーを割けない事態になりかねません。
落とし穴3.条件に合わない協業パートナーと組んでしまう
自社のリソースだけでは検証できない場合、パートナー企業と組むことになりますが、条件に合わないパートナーを選んでしまうことです。
よくある悪い例は、組みやすいからという理由で既存のパートナーを選んでしまうというものです。既存事業でのパートナーとしては実績があっても、新サービスの開発パートナーとしては未知数です。企業間のしがらみなどから、後に引けなくなったり、検証結果が思わしくなくてもサービス案を変更できなくなってしまったりする可能性もあります。
パートナーが大企業の場合、検討初期に求められるスピードや柔軟性が損なわれるリスクもあります。具体的には、打合せの参加者が多く日程調整に時間がかかる、あらゆる意思決定に時間がかかる、リスクや失敗に対して過剰に反応する、などです。
PoCで落とし穴にはまらないための3つのコツ
では、新サービス検討におけるPoCで陥りがちな上記3つの落とし穴を避けるためにはどうすればいいでしょう?ここでは、落とし穴にはまらないためのコツをご紹介します。
誰と一緒に取り組むか ~仲間の選び方~
新サービスの検討メンバーは、先に述べたように、サービス案への想い入れを重視して決めるのが望ましいです。想いがあれば、様々な困難に直面しても、へこたれずに困難を乗り越えていけるでしょう。
チームを組成する方法は大きく2つあります。1つは、サービス案に共感するメンバーを挙手制で募る方法です。この場合は、既存業務との調整に対応するための制度面の設計が必要です。2つ目は、最初から固定メンバーで取り組む方法です。新サービス開発のスキルを高めたい育成対象者が決まっている場合はこちらの方法になります。この場合は、途中でメンバー交代をしないことがポイントです。
サービスに関わる専門性を持つメンバーをアサインしたほうが良いのでは、と疑問を持たれるかもしれませんが、専門性でメンバーを選ぶと、PoCの過程でサービス案を変更する際に「せっかくアサインしたメンバーの専門性が活かせなくなる」といった余計な悩みが生まれてしまうため、お勧めしません。サービス案の修正によって必要な専門性も変わるため、想いを持ったメンバーを核として検討を進め、専門性が必要になったら、その都度、力を借りられるような柔軟な体制や制度が有効です。
アイデアを基にどう動くか ~注力すべきポイント~
PoCでは、早く安く検証することが重要です。なぜなら、PoCにかけられる時間や費用に限りがある中で、検証とサービス改善をどれだけ繰り返せたがサービス案の質に直結するからです。当初思いついたサービス案は未熟であり市場投入できるまで育て上げる必要がありますが、計画やプロトタイプの作り込みをしてもサービス案は育ちません。緻密な計画やプロトタイプ制作にエネルギーを割くよりも、かけられる費用や時間のなかで可能な限り多くの検証(多くの場合はユーザーにぶつけること)を行い、サービス案を育てることに注力すべきです。
例えば新サービス検証初期のぺーパープロトタイプを用いた検証では、できる限り短い時間で検証結果(=ユーザーの反応)を得るため、いかに短時間でサービス案を表現するかに注力します。具体的に言うと、ペーパーにはサービス案のコアとなる要素を表現できていればよいので、フォントやボタンの色やデザインといった細部は作りこみません。
実証実験相手をどう選ぶか ~ビジネスパートナーの選び方~
PoCで協業するパートナーは、フェーズと条件に合わせて選ぶべきです。
新サービス検討初期のPoCであれば、スピーディに柔軟に進められる相手を選ぶことが大切です。スピーディな意思決定が期待できる小規模企業に声をかけるのも一つの手です。社内調整に時間がかからず、企業内の意思決定が早いのが特徴で、実際に成功するケースをいくつも見ています。
大企業の場合、どうしてもスピード感や柔軟性の面で課題が残ります。ある程度現場に権限移譲して頂くなどの前裁きをすべきでしょう。一方で、規模拡大に向けたパートナーであれば、大企業の方が最適候補としてはまるケースが多いです。多少意思決定に時間がかかりますが、決定後は着実に進められます。
もちろん、どこと組む場合でも、実験のリスクや成果をどう扱うのかなどを明確化し、お互いWin-Winとなる関係を組み立てることが大切です。
最後に
いかがでしたしょうか。サービス案への想いを大事にしつつ、できるだけ早く安く検証を進め、サービス案を育てることに時間と費用とエネルギーを注ぐ。PoCで落とし穴に陥らないために大切な要素を感じていただけたでしょうか。
NRIでは、PoCの実行をはじめとした新サービス検討支援、日本企業の特性を踏まえたDX推進支援、DX推進に必要なスキルの習得を支援する「デジタル人材開発プログラム」の提供などを行っています。PoCをはじめとしたDX推進に関してお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。
プロフィール
-
武内 麻里亜
※組織名、職名は現在と異なる場合があります。