コラム
最新のトピックについて、その背景や本質、考え方について、NRIの専門家がわかりやすく解説します。
-

NRI経営コンサルタントの視点
NRIのコンサルタントが、最新ビジネストピックに焦点を当て、その動向や影響を分析・解説 -

木内登英のGlobal Economy & Policy Insight
国内外の経済・金融情勢分析、金融・財政政策評価、マーケット分析など幅広く解説 -

井上哲也のReview on Central Banking
金融政策の狙い、背景、それらが及ぼす影響をどのように解釈すべきか解説 -

大崎貞和のPoint of グローバル金融市場
グローバル金融市場において複雑に絡み合う金融システムの動向を解説 -
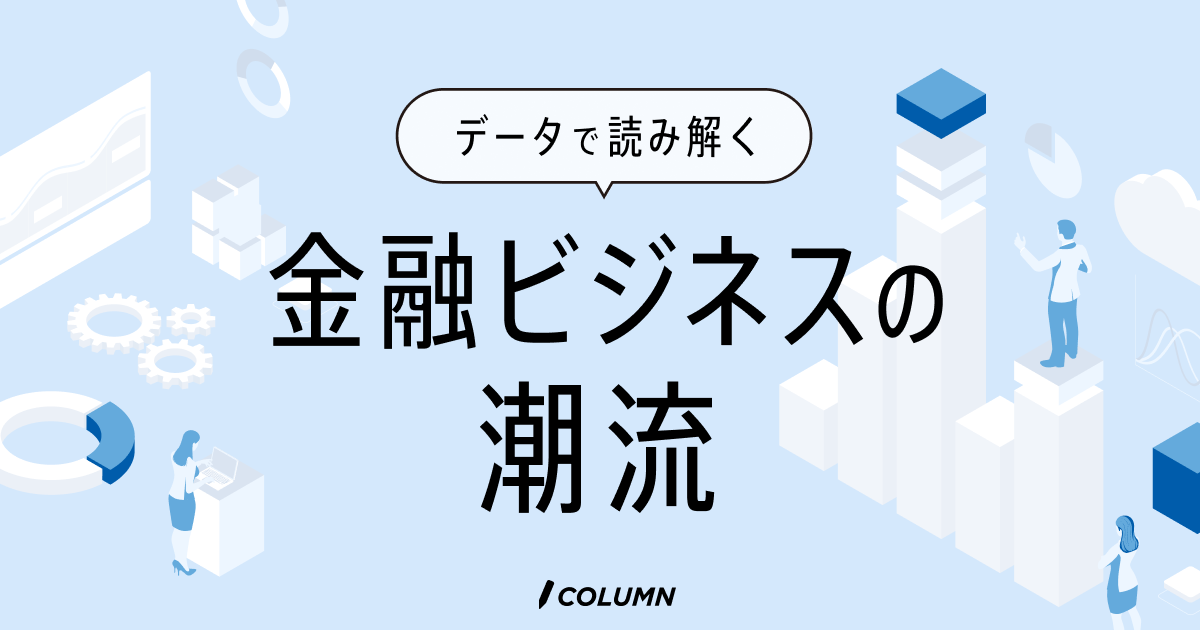
データで読み解く金融ビジネスの潮流
データ分析を通して真実を浮き彫りにし、そこから見えてきた金融ビジネスの潮流を解説 -

神宮健のFocus on 中国金融経済
刻々と変化する中国の金融経済動向を解説 -
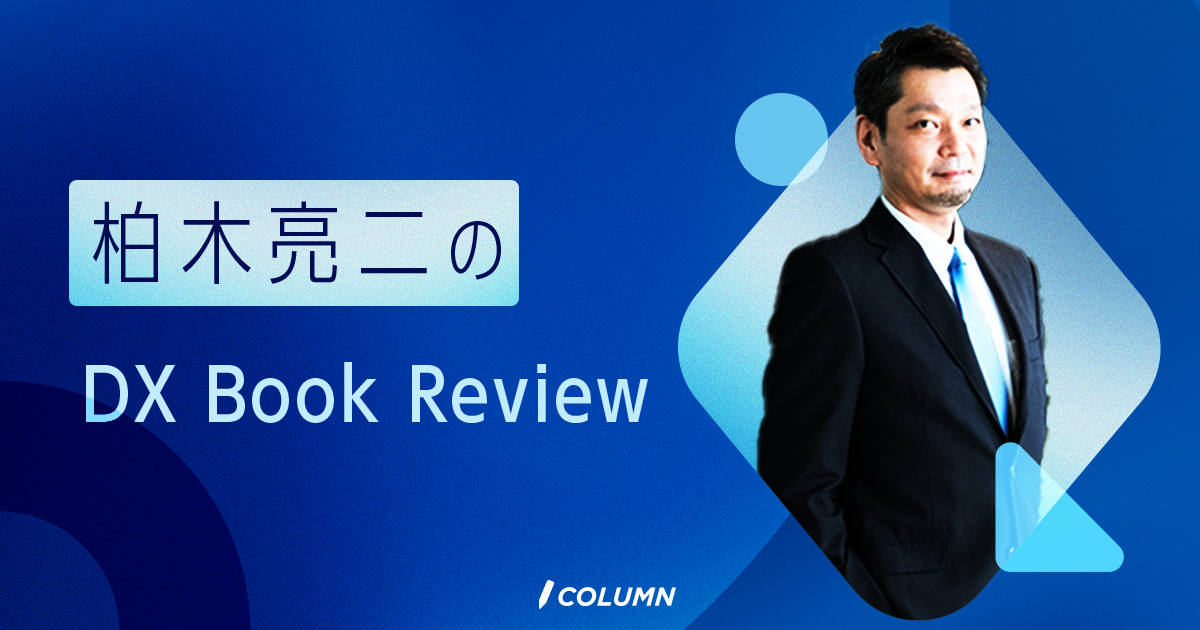
柏木亮二のDX Book Review
DXを理解し、金融ビジネスに生かすヒントとなる本を紹介 -

中国のデジタル経済とチャイナ・イノベーションのトレンド
中国のデジタル経済動向などを独自の視点から解説 -

竹端克利のInsight & Backcasting
金融を取り巻くテーマに対するアイデアやオピニオンを発信 -

DX時代のシステム導入最前線
大規模システムの再構築や運用に長けた腕利きSEがDX実装の裏側を解説 -
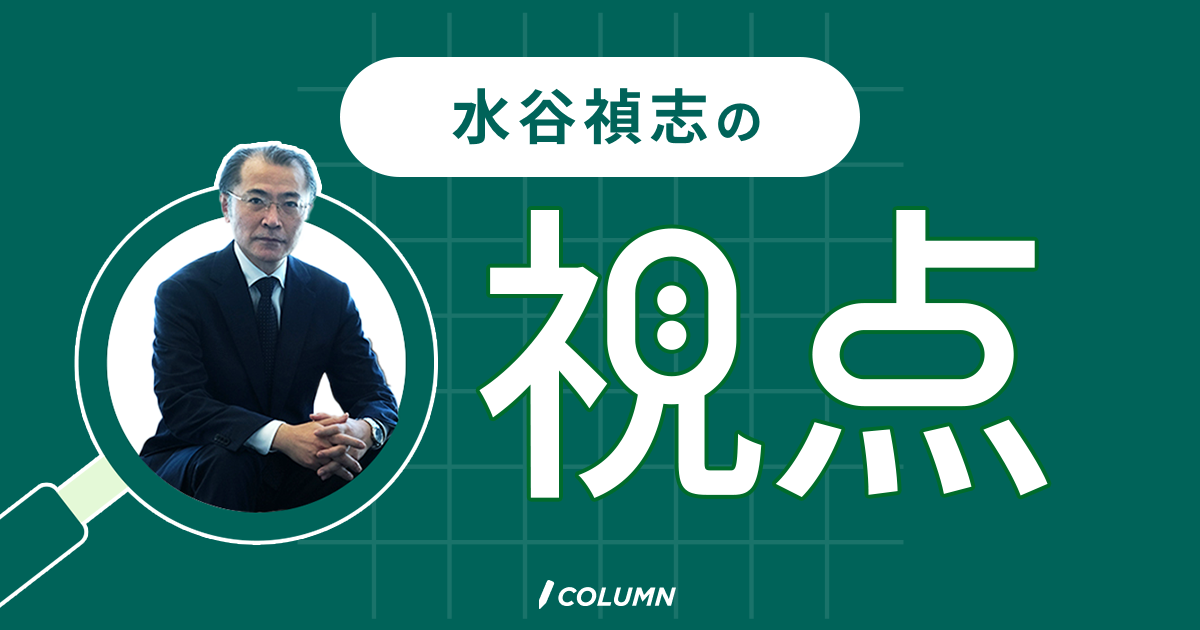
水谷禎志の視点
モノの動きを伴う産業でのDXの動向を解説 -
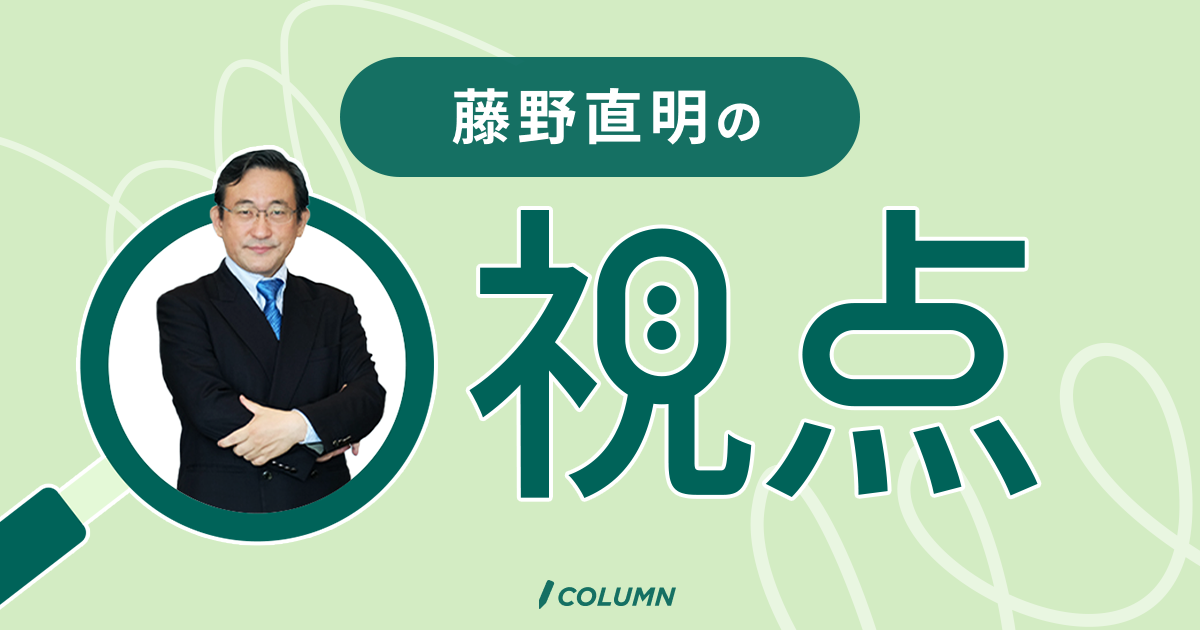
藤野直明の視点
流通業界のDXの取り組みを解説 -

203X : AIで拡張する社会
AIを中心とした新技術が経済・社会に及ぼすインパクトを幅広い視点から解説 -
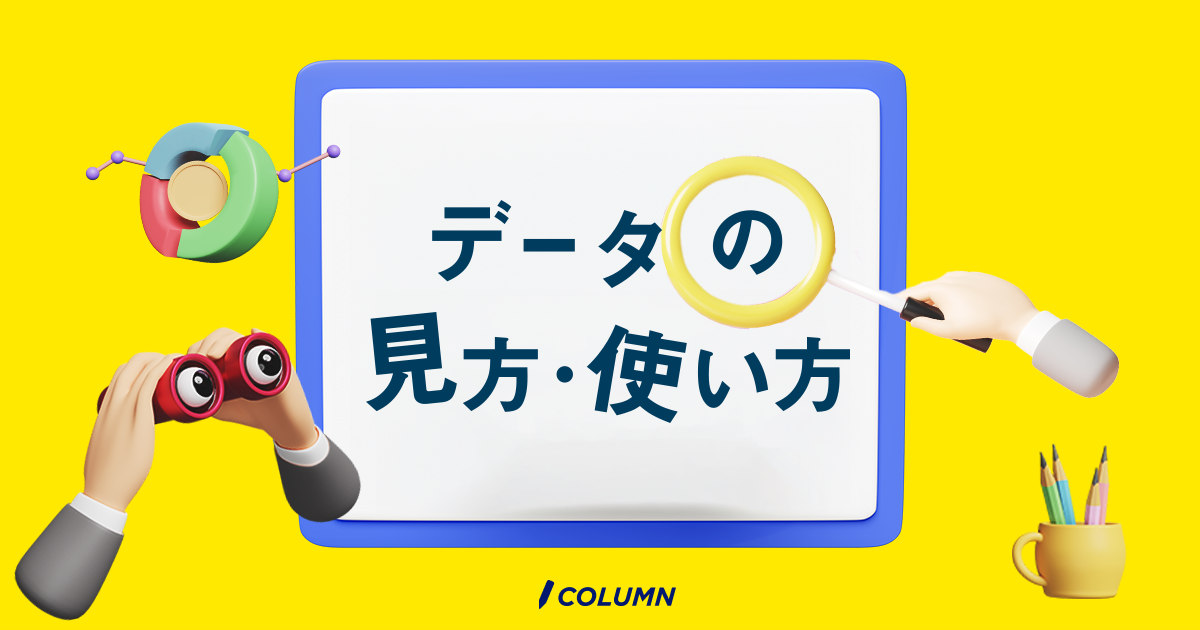
データの見方・使い方
データの中に埋もれている「見えない真実」を掘り起こします -
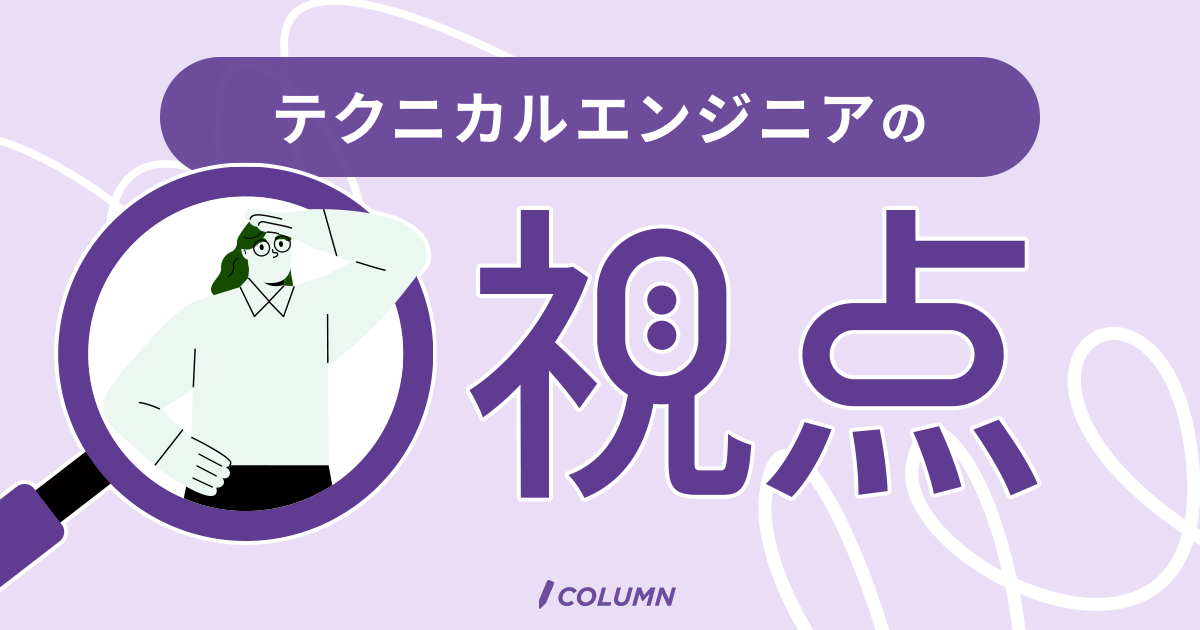
テクニカルエンジニアの視点
先進的な技術を専門家が分かりやすく解説 事業・社会への活用の可能性も紹介 -

NRI Digital Consulting Edge
経験豊富なコンサルタントが、デジタルの急速な変化に対応し、ビジネスを成功に導く方法を解説